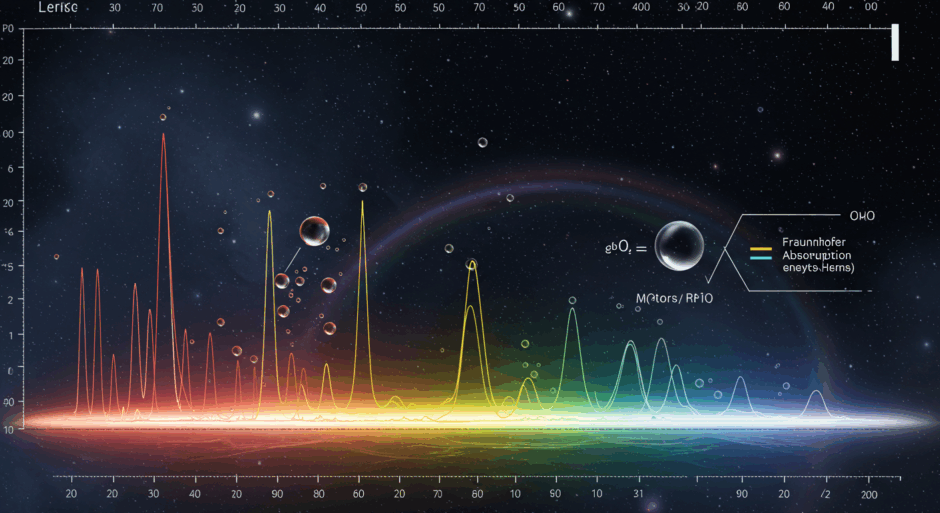※編集部に「やりたい放題やっていい」と言われたので、本当にやりたい放題やります。
7月16日は「虹の日」として知られています。この美しい自然現象は、古来より人々を魅了してきましたが、その背後には深遠な物理学的メカニズムが隠されています。本記事では、高校物理の知識を基盤として、虹の発生原理から最新の量子光学的理解まで、多角的に虹現象を解説します。
今回は「今日は何の日」のコンセプトから少しだけ外れて、物理学としての虹について論じていきます。今回は虹の発生原理と副虹、アレキサンダーの暗帯、過剰虹の発生原理についてふれて日常生活の中の虹について俯瞰するとともに、虹は「太陽光のスペクトル」であるため、当然そこには分光学的、量子論的な示唆があり星の声が聞こえるのです。今回はフラウンホーファー線、黒体輻射に話をしぼって、前期量子論や天体における分子分光学に読者を招待したいと思います。
1.どうして今日は虹の日?
7月16日は「虹の日」として知られています。この記念日は2008年にデザイナーの山内康弘氏によって制定され、「なな(7)いろ(16)」という語呂合わせと、梅雨明けの時期で虹が出現しやすいことが由来となっています。
昔からどの世界や地域においても虹という現象は愛されて、そして神話の中でたびたび登場してきました。私たちも小学生のころ雨上がりに虹がかかると教室の窓から虹を眺めてクラスメイトと盛り上がった経験があるかと思います。誰にだって空を見上げることはできて、そして天に関心を持つものなのでしょう。
翻って、日本では、虹を「蛇」や「龍」の姿として見ていました。「虹」という漢字に「虫」が入っているのも、古代中国で虹を大きな蛇と考えていたことに由来します。また、虹は「天の橋」とも呼ばれ、神々の世界と人間の世界を結ぶ架け橋だと信じられていました。ギリシャ神話では、虹は女神イリスの象徴で、神々のメッセンジャーとされていました。彼女が神々と人間の間をつなぐ橋として虹を使っていたと考えられていました。北欧神話では、虹は「ビフレスト」と呼ばれる神々の住む世界アースガルドと人間界を結ぶ橋でした。旧約聖書では、ノアの箱舟の物語で、大洪水の後に神が「もう二度と大洪水を起こさない」という約束のしるしとして虹を空に架けたとされています。
科学の世界でも虹は、古くから観測されて、そしてなぜ起こるのかについて時代を超えて論じられてきました。アリストテレスの虹理論では、虹は太陽光が雲や水滴に反射することで生まれると考えていました。彼は虹が常に太陽の反対側に現れることを正確に観察し、反射現象であることを理解していました。また、虹の色について「基本的には3色(赤、緑、紫)で、その中間色が混じって見える」と説明しました。古代ローマの学者セネカも『自然問題』で虹を論じ、水滴が関係していることを指摘しました。
13世紀のロジャー・ベーコンは実験を通じて、水晶球に太陽光を当てると虹色が現れることを発見し、虹の実験的研究の先駆けとなりました。
ルネサンス期のレオナルド・ダ・ヴィンチは虹について「太陽と雨と観察者の位置関係」の重要性を認識し、より精密な観察記録を残しました。
ニュートンの貢献は虹の理解において決定的でした。
ニュートンの最大の業績は、1666年頃にプリズムを使った実験で「白色光が7色の光の合成である」ことを証明したことです。彼は太陽光をプリズムに通して虹色のスペクトラムを作り出し、さらにそれをもう一つのプリズムで再び白色光に戻すことで、色の分散と合成を実証しました。
ニュートンが確立した7色は「赤、橙、黄、緑、青、藍、紫」で、これは現在でも使われています。実際には連続的なスペクトラムですが、ニュートンが音楽の7音階との類推から7色に分類したのです。
『光学』(Opticks, 1704年)でニュートンは、虹の色が光の波長の違いによって生まれることを理論的に説明しました。赤い光は屈折率が小さく、紫の光は屈折率が大きいため、雨粒の中で異なる角度で屈折し、分離して見えるのです。
2.虹の発生原理
雨上がりの空に現れる美しい虹は、実は高校物理で学ぶ光学の基本法則によって説明できる自然現象です。一見神秘的に見える虹も、光の屈折、分散、全反射という物理学の原理を理解すれば、その仕組みを完全に理解することができます。
虹が見える条件
虹を観察するためには、太陽光、空気中の水滴、そして観察者の位置という3つの要素が重要です。太陽光が当たっている状況で、雨上がりや霧、滝の水しぶきなどで空気中に小さな水滴が浮遊しており、観察者が太陽を背にして立っているとき、虹を見ることができます。この配置が虹の発生メカニズムと密接に関係しています。
光の屈折と分散の基本原理
虹の根本的な原理は光の屈折と分散にあります。私たちが白色光と呼ぶ太陽光は、実際には赤から紫までの様々な波長の光が混合したものです。これらの異なる波長の光は、同じ媒質中でも微妙に異なる屈折率を示すという重要な性質があります。
スネルの法則(屈折の法則)は
n₁sinθ₁ = n₂sinθ₂
で表されますが、ここで重要なのは屈折率nが光の波長によって変化することです。水の場合、赤色光の屈折率は約1.331、紫色光の屈折率は約1.344となっており、この違いが虹の色分離を生み出す根本的な原因となります。

水滴内での光の複雑な経路
太陽光が水滴に入射すると、まず水滴の表面で屈折が起こります。このとき、波長の違いにより各色の光が異なる角度で屈折し、白色光が色ごとに分離される分散現象が発生します。これは、プリズムで白色光を分光するのと同じ原理です。
水滴内部に入った光は、水滴の後面に到達します。ここで重要な現象が起こります。光が水から空気中に出ようとする際、入射角が臨界角を超えると全反射が発生し、光は水滴内部に反射されます。
臨界角は sinθc = 1/n の関係で決まり、水の場合約48.6度となります。
全反射した光は再び水滴の表面に向かい、今度は水滴から外部に射出されます。この射出時にも再び屈折と分散が起こり、色の分離がさらに強調されます。この一連の過程により、白色光が美しい色彩に分かれて観察者の目に届くのです。

虹の角度と幾何学
虹が見える角度は偶然ではなく、光学的に厳密に決まっています。主虹の場合、赤色光は太陽光の方向から約42度の角度で、紫色光は約40度の角度で観察されます。この角度の違いが、虹の帯の中で外側が赤色、内側が紫色になる理由です。
これらの角度は、太陽光の入射角、水滴の屈折率、そして水滴内での光の経路を幾何学的に計算することで求めることができます。具体的には、光が水滴内で1回全反射を起こす場合の最小偏向角を計算することで導出されます。

虹は円形?
東京大学でも出題された虹の発生原理?
虹の発生原理についてですが、実は2008年に東京大学で入試問題として出題されたことがあります。
筆者は予備校時代に夏期講習でこの問題を解いた思い出があります。上記についてより詳細な導出が行われています。是非説いてみてください。僕は当時解けなくて、、、講義中にぽかーんって聞いていたような気がします。
3.虹にかかわる特殊な現象
3.1副虹
雨上がりの空に美しい虹を見つけたとき、よく注意して観察してみてください。鮮やかな主虹の外側に、もう一つの薄い虹が見えることがあります。この薄い虹を「副虹(ふくにじ)」と呼びます。副虹は主虹よりも暗く、しかも色の順番が逆になっているという不思議な性質を持っています。なぜこのような現象が起こるのでしょうか。高校物理の知識を使って、副虹の謎を解き明かしてみましょう。
副虹の特徴を観察してみよう
副虹には主虹とは大きく異なる特徴があります。まず、副虹は主虹よりも外側、つまり太陽を背にして約51度の方向に現れます(主虹は約42度)。また、色の並び方が主虹と逆になっています。主虹では外側から「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫」の順番ですが、副虹では外側から「紫・藍・青・緑・黄・橙・赤」の順番になります。さらに、副虹は主虹の10分の1程度の明るさしかないため、条件が良くないと見ることができません。
副虹がなぜできるのかを理解するには、水滴の中で光がどのように進むかを考える必要があります。主虹と副虹では、水滴内での光の経路が根本的に異なります。
主虹の場合 太陽光が水滴に入ると、まず水滴の表面で屈折します。次に、水滴の奥で1回だけ全反射を起こし、再び水滴の表面から外に出るときに屈折します。つまり、「入射→屈折→1回反射→屈折→射出」という経路をたどります。
副虹の場合 副虹では、水滴に入った光が2回全反射を起こします。「入射→屈折→1回目の反射→2回目の反射→屈折→射出」という、より複雑な経路をたどります。この2回目の反射が、副虹の特殊な性質を生み出す鍵なのです。
なぜ色の順番が逆になるのか
副虹で色の順番が逆になる理由を理解するために、光の屈折について復習しましょう。水の屈折率は光の色(波長)によって微妙に異なります。前章でも触れた通り、赤色光の屈折率は約1.331、紫色光の屈折率は約1.344です。
主虹では、この屈折率の違いにより、赤色光の方が大きな角度で水滴から出てきます。そのため、虹の外側に赤色が見えます。しかし、副虹では2回の反射により光の進む方向が変わり、今度は紫色光の方が大きな角度で出てくるようになります。この結果、副虹では紫色が外側に、赤色が内側に配置されることになります。

副虹が暗い理由
副虹が主虹よりもずっと暗く見える理由は、物理的に説明できます。光が物質の境界面で反射するとき、毎回少しずつエネルギーを失います。フレネルの反射法則によると、水と空気の境界では約4%の光が失われます。
主虹では水滴内で1回だけ反射しますが、副虹では2回反射します。この追加の反射により、さらに光が失われます。また、2回の反射により光がより広い範囲に散らばってしまうため、同じ方向に向かう光の量が減ります。これらの理由により、副虹の明るさは主虹の約10分の1になってしまいます。
アレキサンダーの暗帯との関係
主虹と副虹の間(約42度から50度の範囲)には、周りより暗い領域があります。これを「アレキサンダーの暗帯」と呼びます。この暗帯ができる理由も、副虹の仕組みと関係しています。
主虹を作る光は42度より大きな角度には届きません。一方、副虹を作る光は50度より小さな角度には届きません。そのため、42度から50度の間は両方の虹からの光が届かず、相対的に暗く見えるのです。この暗帯の存在が、主虹と副虹が別々のメカニズムで作られていることの証拠になっています。
さらに高次の虹も存在する
理論的には、水滴内で3回、4回と反射を繰り返す光によって、さらに高次の虹も作られます。3次虹は太陽の方向約40度に、4次虹は太陽の反対方向約45度に現れると計算されます。しかし、反射回数が増えるほど光は弱くなるため、これらの高次虹を肉眼で見ることは非常に困難です。最近では、高性能なカメラを使って3次虹や4次虹の撮影に成功した例も報告されています。
3.2 過剰虹
美しい虹を写真に撮ったとき、現像やデジタル処理で画像を明るくしてみると、主虹の内側に薄い縞模様が写っていることがあります。この現象を「過剰虹(かじょうにじ)」または「干渉虹(かんしょうにじ)」と呼びます。過剰虹は肉眼では見つけにくく、条件が揃ったときにだけ観察できる特別な現象です。なぜこのような縞模様ができるのでしょうか。実は、これまで学んできた光の屈折や反射だけでは説明できない、光の「波」としての性質が関係しているのです。
過剰虹ってどんな現象?
過剰虹は主虹のすぐ内側に現れる、薄い色の帯が何本も並んだ縞模様です。普通の虹のようにはっきりした色ではなく、白っぽい光や薄い緑、薄い紫などの淡い色が交互に現れます。副虹の外側にも同様の縞模様が現れることがありますが、主虹の内側の方がよく観察されます。
光の波としての性質
過剰虹を理解するには、光が「波」であることを思い出す必要があります。これまで虹の説明では、光を真っ直ぐ進む「光線」として考えてきました。しかし、光は実際には波の性質も持っています。
水面に石を投げ込むと、波紋が広がりますね。もし同時に2つの石を投げ込むと、2つの波紋が重なり合って、波が高くなったり低くなったりする場所ができます。これを「干渉」と呼びます。光の波も同じように、複数の光が重なり合うと干渉を起こします。
水滴の中で何が起こっているのか
過剰虹ができる仕組みを詳しく見てみましょう。太陽光が水滴に入ると、水滴の上の方を通る光と下の方を通る光では、微妙に経路が異なります。
普通の虹の説明では、水滴内での光の経路は1本の線として考えていました。しかし実際には、水滴の様々な場所から光が出てきます。これらの光は、水滴から出た後で重なり合います。
水滴の上部を通った光と下部を通った光は、わずかに異なる距離を進みます。この距離の差により、2つの光波の位相(波の山と谷のタイミング)がずれることがあります。位相がずれた光同士が重なり合うと、干渉が起こります。
干渉の結果、ある方向では光が強め合って明るくなり、別の方向では光が弱め合って暗くなります。この明暗の繰り返しが、過剰虹の縞模様を作り出すのです。
なぜ縞模様になるのか
過剰虹の縞模様は、干渉による明暗のパターンです。主虹の角度(約42度)を中心として、そこから少しずつ角度が変わるにつれて、干渉の条件も変わります
縞の間隔は、光の波長と水滴の大きさによって決まります。水滴が小さすぎると縞模様は現れず、大きすぎると縞が細かくなりすぎて見えなくなってしまいます。適度な大きさの水滴(直径0.5〜1mm程度)のときに、最も美しい過剰虹が観察できます。
水滴の大きさが重要な理由
過剰虹が見えるかどうかは、空気中の水滴の大きさに大きく依存します。これは光の回折という現象と関係があります。
大きな水滴の場合:光の波長に比べて水滴が十分大きいと、光は幾何光学的に進み、干渉効果は目立ちません。普通の虹は見えますが、過剰虹は現れません。
小さな水滴の場合:水滴が光の波長に近いほど小さいと、光は大きく散乱されてしまい、虹自体がぼやけてしまいます。
適度な大きさの水滴の場合:水滴の大きさが光の波長の数千倍程度のとき、幾何光学的な虹と波動光学的な干渉効果の両方が現れ、美しい過剰虹が観察できます。
4.量子論と太陽光
虹は太陽の光です。ここで恒星の光について量子論に基づいた説明をしていきたいと思います。(!?)
4.1 太陽光の温度と太陽の色
夜空を見上げると、星によって色が違うことに気づくでしょうか。赤っぽい星、青白い星、黄色い星など、様々な色の星が輝いています。また、私たちの太陽も黄色っぽく見えますが、宇宙から見ると実は白色です。これらの色の違いは偶然ではありません。実は、星の色はその星の「温度」を直接表しているのです。この不思議な関係を理解する鍵が「黒体輻射(こくたいふくしゃ)」という物理現象です。今回は、なぜ温度によって色が変わるのか、そしてそれが星の観測にどのように役立っているかを探ってみましょう。
温度と色の不思議な関係
まず、身近な例から考えてみましょう。鉄を熱すると、最初は黒いままですが、温度が上がるにつれて赤く光り始め、さらに熱すると白っぽくなります。これは鉄の材質が変わるからではなく、温度が変わることで放出される光の色が変化するからです。
この現象は規則的な順序で起こります。約500℃では暗い赤色を示し、約700℃になると明るい赤色になります。さらに温度が上がって約1000℃ではオレンジ色、約1200℃では黄色、約1500℃では白色を示すようになります。さらに高温になると青白色を放出します。つまり、物体の温度が高くなるほど、放出される光の色は赤から青へと変化するのです。この法則は宇宙のどこでも同じように成り立ちます
黒体輻射とは何か
「黒体輻射」とは、温度を持つ物体が放出する光(電磁波)の性質を表す物理法則です。「黒体」とは、あらゆる波長の光を完全に吸収する理想的な物体のことを指します。この黒体という概念は、物理学的に非常に重要な意味を持っています。
黒体には重要な性質があります。温度が絶対零度(マイナス273℃)より高ければ、必ず光を放出します。そして、放出される光の強さと色は、温度だけで決まり、材質や大きさには関係しません。実際の星は完全な黒体ではありませんが、黒体輻射の法則にとてもよく従います。そのため、星の色を観測することで、その星の表面温度を正確に知ることができるのです。

プランクの法則:温度と光の関係式
20世紀初頭、ドイツの物理学者マックス・プランクは、黒体輻射を完全に説明する法則を発見しました。この「プランクの法則」によると、温度Tの黒体が放出する光の強さは、光の波長によって決まる特定の分布を示します。
この法則から、非常に重要な結論が導かれます。まず「ウィーンの変位法則」では、最も強く放出される光の波長は、温度に反比例することが示されます。つまり、温度が高いほど短い波長である青い光が強くなります。また「ステファン・ボルツマンの法則」では、物体が放出する全エネルギーは、温度の4乗に比例することが示されます。これは、温度が2倍になると、放出エネルギーは16倍になることを意味しています。
太陽の色と温度
私たちの太陽は、地球から見ると黄色っぽく見えますが、実際の色は白色です。地球の大気が青い光を散乱させるため、黄色っぽく見えているのです。太陽の表面温度は約5778K(5505℃)で、この温度での黒体輻射を計算すると、最も強く放出される光の波長は約500ナノメートル、つまり青緑色の範囲になります。
しかし、太陽は幅広い波長の光を放出しており、紫外線が約10%、可視光線が約45%、赤外線が約45%という割合ですべての色が混ざることで白色光となります。この分布は、5778Kの黒体輻射の理論値とほぼ完全に一致しており、太陽が黒体輻射の法則に非常によく従っていることを示しています。
星の色が教える温度の秘密
星を望遠鏡で観測すると、様々な色の星が見えます。それぞれの色は、その星の表面温度を直接表しています。青白い星は非常に高温で、表面温度が20,000Kから50,000K以上に達します。リゲルやスピカなどがこの分類に属し、非常に高温で明るいが、寿命が短いという特徴があります。
白い星は表面温度が7,000Kから20,000Kの範囲にあり、シリウスやベガなどが代表例です。これらの星は高温で明るく輝いています。黄色い星は表面温度が5,000Kから7,000Kで、私たちの太陽やアルファ・ケンタウリAがこの分類に属します。これらの星は安定して長時間輝く特徴があります。
オレンジ色の星は表面温度が3,500Kから5,000Kで、アルクトゥルスやアルデバランなどが該当します。比較的低温で寿命が長いのが特徴です。最も低温なのが赤い星で、表面温度は2,000Kから3,500Kです。ベテルギウスやアンタレスなどがこの分類に属し、低温で赤く、非常に長寿命という特徴を持っています。
なぜ星によって温度が違うのか
星の温度は、主にその星の「質量」によって決まります。質量が大きな星ほど、中心部での核融合反応が激しく起こり、表面温度も高くなります。太陽の10倍の質量を持つ星では表面温度が約25,000Kに達して青白色を示し、太陽と同じ質量では約5,800Kで黄色、太陽の半分の質量では約3,000Kで赤色を示します。
ただし、星の進化段階によっても温度は変化します。年老いた星は膨張して表面温度が下がり、赤色巨星になることがあります。このように、星の色は単に現在の状態だけでなく、その星の一生の物語をも語っているのです。
黒体輻射から始まった量子論
黒体輻射の研究は、20世紀物理学の革命の出発点となりました。プランクが黒体輻射を説明するために導入した「量子」の概念は、後に量子力学の基礎となりました。この発見は量子力学の誕生につながり、原子構造の理解を深め、現代の電子技術の基礎を築き、宇宙の理解を大きく進歩させました。
温度を測る宇宙の温度計
黒体輻射の法則により、天文学者は遠い星の温度を正確に測定できます。これは、星までの距離が何光年離れていても可能です。色を調べるだけで温度がわかるのですから、まさに「宇宙の温度計」と言えるでしょう。この技術により、星の進化段階、星の寿命の予測、惑星が生命に適した温度かの判断、銀河系の構造と進化の理解が可能になりました。
現代技術への応用
黒体輻射の理論は、現代の様々な技術に応用されています。赤外線温度計は物体が放出する赤外線を測定して、非接触で温度を測る技術として広く使われています。
熱画像カメラは物体の温度分布を色で表示する技術として、医療や建築分野で活用されています。LED照明の開発では自然な光の色を再現するために、また宇宙望遠鏡では遠い天体の温度と組成を調べるために、この理論が重要な役割を果たしています。
宇宙背景放射:ビッグバンの残光
黒体輻射の最も壮大な応用例は、「宇宙背景放射」の発見でしょう。1965年、アメリカの科学者ペンジアスとウィルソンは、電波望遠鏡で宇宙からやってくる微弱な電波を発見しました。この電波は宇宙のあらゆる方向から均等にやってきており、その特徴を詳しく調べると、温度約2.7Kの黒体輻射であることがわかりました。
この発見は、宇宙の始まりに関する重要な証拠となりました。ビッグバン理論によると、宇宙は約138億年前に非常に高温・高密度の状態から始まり、その後膨張し続けています。宇宙の初期は数千度の高温状態でしたが、膨張により温度が下がり、現在では絶対零度に近い約2.7Kまで冷却されています。
宇宙背景放射は、まさにこの「ビッグバンの残光」なのです。初期宇宙の高温状態で放出された光が、宇宙の膨張により波長が引き延ばされ(赤方偏移)、現在では電波の領域まで長くなって観測されています。この現象により、私たちは宇宙の歴史を直接観測することができるのです。
興味深いことに、宇宙背景放射のスペクトルは理論的に予測された黒体輻射のカーブと完璧に一致しています。これは、宇宙が一様で等方的であること、そしてビッグバン理論の正しさを強く支持する証拠となっています。
4.2フラウンホーファー線と太陽光
太陽の光をプリズムで分けると、美しい虹色のスペクトルが現れます。しかし、このスペクトルをよく観察すると、連続した虹色の中に無数の細い黒い線が混じっていることがわかります。これらの黒い線を「フラウンホーファー線」と呼びます。19世紀初頭、ドイツの物理学者ヨーゼフ・フォン・フラウンホーファーによって詳しく研究されたこの現象は、太陽や星の中にどんな元素が含まれているかを教えてくれる「宇宙の化学分析」を可能にしました。なぜ太陽光の中に黒い線が現れるのでしょうか。そして、この発見はどのように天文学を革命的に変えたのでしょうか。
フラウンホーファーの偉大な発見
1814年、フラウンホーファーは太陽光を高性能なプリズムで詳しく調べていました。当時の技術では最高精度の分光器を使って観察した結果、太陽光のスペクトルの中に574本もの暗い線があることを発見しました。この発見は驚くべきものでした。なぜなら、当時の人々は太陽光が完全に連続したスペクトルを持つと考えていたからです。
フラウンホーファーは主要な線にA、B、C、D、E、F、G、Hというアルファベットで名前をつけました。これらの名前は今でも使われており、たとえばフラウンホーファーD線は波長589.3ナノメートルのナトリウムによる吸収線、C線は656.3ナノメートルの水素による吸収線を指しています。この系統的な観察と分類が、後の分光学発展の基礎となったのです。

黒い線ができる仕組み
フラウンホーファー線がなぜできるのかを理解するには、原子の構造を知る必要があります。原子は中心に原子核があり、その周りを電子が回っています。電子は特定のエネルギー状態(エネルギー準位)しか取ることができません。電子がより高いエネルギー状態に移るとき、その差に相当するエネルギーの光を吸収します。
重要なのは、各元素が独特のエネルギー準位を持つことです。そのため、特定の波長の光だけが吸収され、吸収される波長は元素によって決まります。これはまさに「元素の指紋」のように働きます。
太陽光のフラウンホーファー線ができる過程を詳しく見てみましょう。まず太陽の中心部では、核融合反応により連続スペクトルの光が生成されます。この光が表面に向かって進む間、太陽内部の様々な元素の原子が特定の波長の光を吸収します。さらに太陽の表面(光球)では温度が約5800Kと比較的低く、ここでも元素による光の吸収が起こります。最終的に太陽の大気(彩層・コロナ)でも吸収を受けた光が地球に届き、フラウンホーファー線として観測されるのです。
吸収と発光
実験室で元素を熱すると、その元素特有の波長の光を発光します。この発光スペクトルと呼ばれる現象には、重要な法則があります。同じ元素が吸収する光の波長と発光する光の波長は全く同じなのです。これを「キルヒホフの法則」と呼びます。
たとえばナトリウムは589.3ナノメートルの黄色い光を発光しますが、同じナトリウムは589.3ナノメートルの光を吸収します。この吸収がフラウンホーファーD線を作り出すのです。この関係により、地球上の実験室で測定した元素の発光スペクトルと、太陽光で観測される吸収スペクトルを比較することで、太陽にどんな元素が含まれているかがわかるようになりました。
宇宙の化学組成を読み解く
フラウンホーファー線の強さを測定することで、太陽や星の化学組成を定量的に調べることができます。線の強さには様々な要因が影響します。まず、その元素が多いほど、対応する吸収線は強くなります。また、温度によって原子の励起状態が変わり、吸収線の強さも変化します。さらに、ガスの密度が高いほど、吸収は強くなります。
これらの解析により、太陽の化学組成が明らかになりました。太陽は質量比で約73%が水素、約25%がヘリウム、残り約2%が酸素、炭素、鉄などの重元素で構成されています。この組成は、宇宙全体の平均的な元素組成とほぼ一致しており、太陽が宇宙の典型的な星であることを示しています。
ヘリウムの発見:太陽で見つかった元素
フラウンホーファー線研究の最も劇的な成果の一つが、ヘリウムの発見です。1868年、日食の際に太陽のコロナのスペクトルを観測していた天文学者たちは、地球上の既知の元素では説明できない黄色い発光線(587.6ナノメートル)を発見しました。
この未知の線は、地球上のどの元素の線とも一致せず、太陽の高温環境でのみ観測される非常に強い発光を示しました。科学者たちは、これが新しい元素による線だと結論し、太陽の神ヘリオスにちなんで「ヘリウム」と名付けました。
興味深いことに、ヘリウムが地球上で発見されたのは、太陽での発見から27年後の1895年のことでした。ウランなどの放射性元素から放出されるα線の正体がヘリウムの原子核であることがわかり、ついに地球上でもヘリウムが確認されました。ヘリウムは「宇宙で発見されてから地球で見つかった唯一の元素」という記録を持っています。
星の運動を測る:ドップラー効果の応用
フラウンホーファー線は、星の運動を測定する道具としても使われます。救急車のサイレンが近づくときに音が高く聞こえ、遠ざかるときに低く聞こえる現象をドップラー効果と呼びますが、光でも同じ現象が起こります。
星が地球に近づくとスペクトル線が短波長側(青側)にずれ(青方偏移)、星が地球から遠ざかるとスペクトル線が長波長側(赤側)にずれます(赤方偏移)。この効果により、地球に向かう、または地球から遠ざかる星の視線速度を正確に測定できます。
この技術は様々な天文学的発見に活用されています。2つの星が互いの周りを回る連星系では、スペクトル線が周期的にずれることで連星の存在がわかります。さらに重要なのは、惑星の重力により星がわずかに揺れると、そのドップラー効果から惑星の存在を検出できることです。これが系外惑星発見の主要な手法の一つとなっています。また、遠い銀河のスペクトル線の赤方偏移から、宇宙の膨張という驚くべき事実が発見されました。
https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/theory/theory01.html
現代の分光学への発展
フラウンホーファーの発見は、現代の天文分光学の基礎となりました。現代の分光器では、フラウンホーファーが発見した574本をはるかに超える、数万本の吸収線を検出できます。デジタル技術により、微弱なスペクトル線も正確に測定できるようになり、宇宙望遠鏡では地球大気の影響を受けずに、紫外線や赤外線のスペクトルも観測可能です。
これらの技術により、恒星の進化、銀河系の構造、宇宙の年齢測定、そして生命探査まで、幅広い研究が可能になりました。星の温度、密度、化学組成の変化を追跡し、星の一生を理解できるようになりました。様々な星の化学組成から、銀河系の形成と進化も解明されつつあります。最古の星の重元素含有量から、宇宙の年齢を推定することもできます。
5.まとめ
やりたい放題やって申し訳ございません…