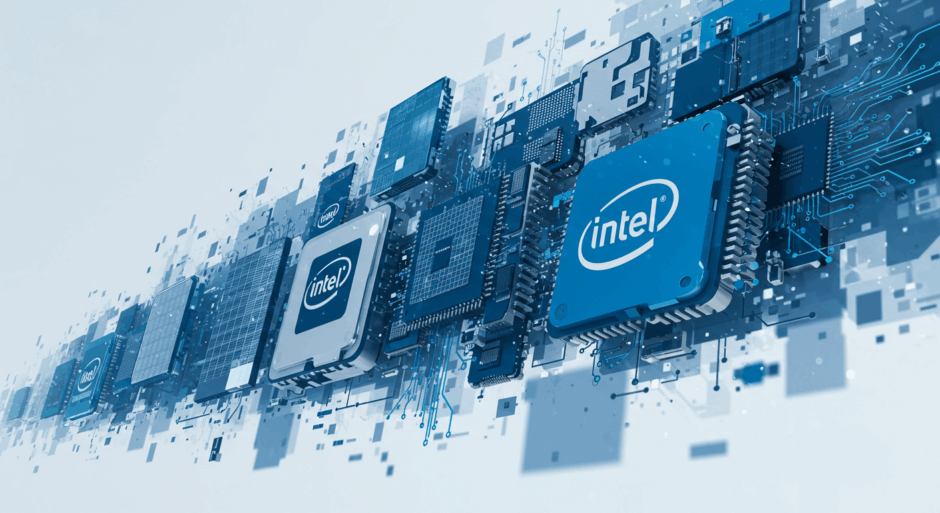はじめに
1968年7月18日、フェアチャイルドセミコンダクターを退職したロバート・ノイスとゴードン・ムーア(ムーアの法則で知られる)らによって、世界最大の半導体メーカーとなったIntel社が誕生しました。今から57年前の出来事です。
「インテル、はいってる」というキャッチフレーズで親しまれ、パソコンの心臓部として私たちの生活に欠かせない存在となったIntelの歩みを振り返りながら、競合他社との激しい競争や、AI時代における新たな挑戦について詳しく見ていきましょう。
Intel社の概要と創業の経緯
創業の背景と設立
Intel Corporationは1968年7月18日、フェアチャイルドセミコンダクターを退職したロバート・ノイスとゴードン・ムーアらによって設立されました。社名の由来は「Integrated Electronics(集積されたエレクトロニクス)」です。
興味深いエピソードがあります。当初は、ゴードン・ムーアとロバート・ノイスの名前を組み合わせて「Moorenoyce」という社名を考えていましたが、ホテルチェーンで同名の会社が既に登記されていたため、「Intel」という名前になったそうです。
創業者の一人であるゴードン・ムーアは、半導体の集積密度が18〜24ヶ月で倍増するという「ムーアの法則」で知られています。この法則は今日まで半導体業界の指針となっています。そして3番目の社員としてアンドルー・グローヴが入社したことで、後にIntelの経営を支える強力なトリオが揃うことになりました。
なお、アンドルー・グローヴについては、1968年に社内の関係悪化を理由にロバート・ノイス、ゴードン・ムーアとともにフェアチャイルド・セミコンダクターを去りました。ノイスとムーアがインテルを設立した際、グローヴは創業には関わりませんでしたが、3番目の社員として設立当日に入社したという経緯があります。
初期の事業展開
当初のIntelは半導体メモリを主力製品とし、磁気コアメモリの置き換えを目指していました。順調に革新的な製品を市場に送り出していきます。
1969年4月にはIntel初の製品であるSRAM 3101を発表(記憶容量64ビット)。翌1970年10月には世界初のDRAM 1103を発表(記憶容量1,024ビット)しました。
そして1971年、半導体業界、ひいてはコンピュータ業界全体に革命をもたらす製品が誕生します。1971年11月15日、世界初のマイクロプロセッサである4004(4ビット、クロック周波数108 kHz、トランジスター数2,300個)を発表したのです。この4004こそが、現在のCPUの原点となった記念すべき製品でした。
PC時代の到来とIntelの飛躍
1980年代に入ると、Intelにとって運命的な出来事が起こります。1981年8月、IBMが同社初のパソコン「IBM PC」を発表し、CPUに8088が採用されました。これがIntelの急成長のきっかけとなったのです。
IBM PCの成功により、Intelの8086系アーキテクチャは業界標準となり、「x86アーキテクチャ」として現在まで続く地位を確立しました。
1985年10月、IntelはDRAM事業から撤退し、CPUの開発・生産に経営資源を集中させる決断を下します。同時に、x86シリーズでは初の32ビットマイクロプロセッサであるi386を発表しました。この決断こそが、Intelを世界最大のCPUメーカーへと押し上げる分岐点となったのです。
競合他社との激烈な競争史
AMD – 最大のライバルとの長きにわたる戦い
セカンドソース時代から独立路線へ
IntelとAMDの関係は、意外にも協力関係から始まりました。1982年、AMDはセカンドソースの一員として、インテルCPUの生産を開始。1984年にはインテルの80286と完全互換のCPUを出荷しました。
IBM PCとMS-DOSの組み合わせが標準パソコンとしての地位を確立すると、8086に基づいた「x86アーキテクチャー」が世界標準になっていきます。このときまでは、IntelとAMDは”x86同盟”の下で手を組み、競合する米モトローラなどに対抗していました。
しかし、Intelは1985年に発表した「Intel 386プロセッサ」以降、セカンドソースを認めない方針に切り替え、半導体を作るのに必要な重要資料を公開しなくなりました。これがIntelとAMDの決別の決定的な転換点となりました。
独自路線での競争激化
1991年、AMDは最初の互換プロセッサとして「Am386」を製造・販売しますが、Intelは既に次世代CPUの「i486」シリーズを販売していました。「Am386」は旧世代でしたが、低価格製品として採用されました。この頃から、AMDは「高性能・低価格」という独自のポジショニングを確立していくことになります。
「ギガヘルツ争」とAthlonの登場
1990年代後半から2000年にかけて起こった「1GHz」を目指す戦いは、両社のブランドイメージをかけた総力戦となりました。2000年頃、Intel社は「Pentium III」で1GHzを達成。一方のAMDも、負けじと「Athlon」で1GHzを達成します。
特にデュアルコア時代に突入すると、2005年5月には初のPC用デュアルコアCPUである「Pentium D」がリリースされ、それに対抗するように翌月には「Athlon 64 X2」がリリースされるなど、両社一歩も譲らない性能競争が繰り広げられました。
驚くべきことに、この時点でAMDが性能と消費電力、発熱の低さでIntelを一歩リードし、世界の巨人Intelが業界2位のAMDに敗れるという前代未聞の事態が発生しました。これは半導体業界史上、極めて稀な出来事でした。
Coreシリーズによる復活とRyzenの反撃
一時はAMDの後塵を拝したIntelですが、新たなブランド「Coreシリーズ」の開発によって再び業界のトップに君臨します。「Core」「Core 2 Duo」「Core 2 Quad」「Core iシリーズ」と進化を続け、2000年代中盤以降は事実上、AMDが追いつくことのできない壁となった状況が長く続きました。
一時期AMDは高性能CPU市場からの事実上の撤退を余儀なくされました。しかし、2017年にAMDが投入したRyzenシリーズは、この状況を劇的に変えました。AMDは近年、Ryzenシリーズで大きな進歩を遂げ、Intel製CPUと互角以上の性能を示すようになりました。特に、マルチコア性能、電力効率、コストパフォーマンスでAMDは優位性を持っています。
市場シェアの逆転
そして2021年、ついに歴史的な変化が起こります。2021年1〜3月のCPU市場シェアにおいて、AMDが50.7%となり、Intelを超えたことが明らかになりました。さらに、AMDが時価総額でIntelを逆転したという企業価値の面でも歴史的な転換点を迎えています。
NVIDIA – GPU分野からAI時代の覇者へ
グラフィックス分野での競争
当初、IntelとNVIDIAの関係は、CPUとGPUという異なる市場での棲み分けが明確でした。「GPU」とは、グラフィックボードに搭載されている演算用のプロセッサで「Graphics Processing Unit」の略称です。GPUメーカーの大手として「NVIDIA」「AMD」「Intel」が存在していますが、NVIDIAが圧倒的な存在感を示してきました。
AI時代の到来とNVIDIAの躍進
GPUは浮動小数点演算を高速に実行することに特化した機能を持っているという特性が、AI時代において決定的な意味を持つことになります。GPUを使えば、CPUの数十倍の速度で学習を行うことができます。例えば、これまで1回の学習に1週間かかっていたものが、GPUを使えば半日で終わるようになるのです。
NVIDIAはデータセンターGPU市場で圧倒的なリードを誇り、市場シェアの92%を占めています。2023年の四半期売上高は、第1四半期の43億米ドル規模から、第4四半期の160億米ドル規模へと飛躍(272%増)しました。この急成長は、生成AIブームによるものです。
Intelの苦戦とNVIDIAの圧倒的優位
NVIDIAとAMDの旧来の競合相手であるIntelは、データセンターGPU分野では後れを取っています。データセンター向けにAIサーバの需要が伸びている昨今において、Intelのデータセンター向け売上高は伸び悩むどころか下落基調にあります。サーバーの「常識」が激変する中、NVIDIAのGPUがIntelのCPUを圧倒するという状況が現実のものとなっています。
Intelの現在の挑戦と未来への取り組み
業績の現状と課題
Intelは現在、厳しい状況に直面しています。2024年第1四半期(1〜3月)より営業赤字および当期赤字が拡大していること、第3四半期の見通しが良くないことなどがネガティブに評価され、Intelの株価は大きく下落しました。
もともとIntelは、四半期の売上高が200億米ドル前後に達していましたが、昨今では150億米ドルをなかなか超えることができず、赤字計上に陥っているという深刻な状況にあります。特に、かつては四半期で60億米ドル以上の売上高を計上していたデータセンター分野で、今ではその半分しかないという苦戦が目立ちます。
構造改革と将来への布石
こうした状況を受けて、業績悪化を受けたIntelは、2025年までに100億ドルのコスト削減を進めるという大規模な構造改革に着手しています。
また、2024年12月に退任したパット・ゲルシンガー前CEOに代わり、2025年3月、ケイデンス(CDNS)の元CEO、リップ・ブー・タン氏を新CEOに指名するなど、経営陣の刷新も図られています。
AI PC時代への対応
一方で、Intelも新たな時代への適応を図っています。AI PCの中核となるのは、そのプロセッサです。AI PC向けとして登場したIntel Core Ultraプロセッサでは、従来のCPUとGPUに加え、AI専用プロセッサとなるNPUを搭載するなど、AI時代に向けた技術革新を進めています。
業界全体への影響と今後の展望
競争がもたらした技術革新
これらの企業が激しい競争を繰り広げることで、CPUの性能は飛躍的に向上し、高性能な製品を安価に入手できるようになりました。これはまさに競争の恩恵を示しています。AMDの躍進は、CPU市場に健全な競争をもたらし、技術革新を加速させていることは間違いありません。
多極化する半導体市場
現在の半導体市場は、単純な二強構図から複雑な多極化の様相を呈しています。半導体業界において、Nvidia、AMD、Intelの3社は、その革新性と技術力で市場をリードする主要な企業です。それぞれが独自の製品と技術を持ち、多様な用途と市場ニーズに応えています。
CPU分野ではIntelとAMDが、GPU分野ではNVIDIAが、そしてAI分野では各社が異なるアプローチで競争を繰り広げています。この多様性こそが、技術革新の源泉となっているのです。
おわりに
1968年7月18日に産声を上げたIntelは、半導体業界の発展とともに歩み、時にはその牽引役となり、時には激しい競争にさらされながらも、常に技術革新の最前線に立ち続けてきました。「ムーアの法則」に象徴される技術の指数関数的進歩は、IntelのDNAに深く刻まれているといえるでしょう。
現在、AI時代の到来という新たな転換点を迎える中で、Intelは過去の栄光にとらわれることなく、変革への挑戦を続けています。AMDとの熾烈な競争、NVIDIAのGPU分野での圧倒的優位という現実を受け入れながらも、新たな技術領域での巻き返しを図っています。
「インテル、はいってる」というキャッチフレーズが示すように、Intelは長年にわたって私たちの身近な存在であり続けてきました。創業から57年を迎えた今日、同社がどのような新たな章を刻んでいくのか、その行く末に注目が集まります。技術革新への飽くなき挑戦と、競争による切磋琢磨こそが、半導体業界全体の発展を支えているのです。