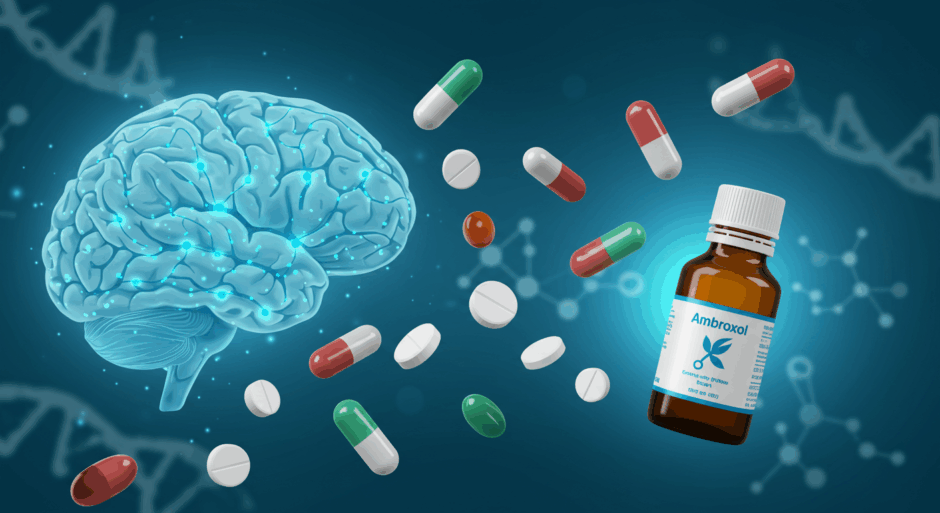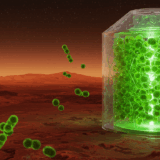カナダのウェスタン大学のスティーブン・パスターナック神経科医が主導した第2相臨床試験の結果が発表された。パーキンソン病認知症患者55名を対象とした52週間の二重盲検プラセボ対照試験である。
アンブロキソールは1979年から欧州で咳止め薬として使用されている薬物で、米国、カナダ、オーストラリアでは未承認である。試験では22名がアンブロキソール高用量を1年間服用し、25名がプラセボを服用した。
結果として、プラセボ群は神経精神症状スコアが平均3.73ポイント悪化したが、アンブロキソール群は平均2.45ポイント改善した。アンブロキソール服用者は妄想、幻覚、不安、易怒性、無関心、異常運動活動の症状が安定化し、転倒回数も減少した。また、アンブロキソール服用者のグルコセレブロシダーゼ(GCase)酵素活性は1.5倍に増加した。
高リスクGBA1遺伝子変異を持つ一部の参加者でアンブロキソール服用により認知機能改善が見られたが、サンプル数が少なく対照群がないため追加研究が必要である。軽度から中等度の胃腸障害により数名が試験を中止したが、重篤な副作用は報告されなかった。
From:  Cough Medicine May Protect Against Some of Parkinson’s Worst Symptoms
Cough Medicine May Protect Against Some of Parkinson’s Worst Symptoms
【編集部解説】
ドラッグリポジショニングの新たな可能性
今回のアンブロキソール研究は、既存薬物の新用途発見、いわゆる「ドラッグリポジショニング」の典型例として注目すべき事例です。1979年から咳止め薬として使用されてきた薬物が、40年以上を経てパーキンソン病認知症の治療薬候補として浮上したことは、医薬品開発の新たなアプローチを示唆しています。
特に興味深いのは、この発見が偶然ではなく、GBA1遺伝子とグルコセレブロシダーゼ(GCase)酵素の関係性を基盤とした科学的根拠に基づいている点です。アンブロキソールがGCase活性を1.5倍に増加させるという具体的なメカニズムが解明されており、これは単なる症状緩和ではなく、疾患の根本的な病理プロセスに介入する可能性を示しています。
神経変性疾患治療のパラダイムシフト
従来のパーキンソン病治療は主に症状管理に焦点を当てていましたが、アンブロキソールは疾患修飾療法(Disease-Modifying Therapy)としての可能性を秘めています。神経精神症状の安定化は、脳細胞保護効果を示唆する重要な発見といえるでしょう。
現在進行中の第3相試験ASPro-PDでは、より大規模な検証が実施されており、これが成功すれば神経変性疾患治療の新たな標準となる可能性があります。特にGBA1遺伝子変異保有者における認知機能改善の兆候は、個別化医療の観点からも重要な意味を持ちます。
技術的な課題と限界
一方で、今回の研究には重要な限界も存在します。第2相試験の参加者数は55名と比較的少なく、主要評価項目である認知機能改善については統計的有意差が確認されていません。また、軽度から中等度の胃腸障害により数名が試験を中止したことも、実用化に向けた課題として認識すべきでしょう。
さらに、アンブロキソールが米国、カナダ、オーストラリアで未承認である点は、グローバルな治療アクセスの観点から重要な制約となります。これらの国々での承認プロセスには、追加の安全性データや規制当局との調整が必要となるでしょう。
規制環境への影響
この研究成果は、既存薬物の新用途開発に関する規制フレームワークにも影響を与える可能性があります。特に、長期間の安全性データが蓄積された薬物の再評価プロセスや、希少疾患治療薬としての迅速承認制度の活用が注目されます。
また、バイオマーカーを用いた治療効果判定の重要性も浮き彫りになっており、今後の臨床試験設計や薬事承認プロセスにおいて、従来の症状評価に加えて生化学的指標の活用が拡大する可能性があります。
長期的な展望と社会的インパクト
アンブロキソールの成功は、他の神経変性疾患への応用可能性も示唆しています。筋萎縮性側索硬化症(ALS)、ゴーシェ病、神経炎症、脊髄損傷など、幅広い疾患への治療応用が期待されており、これは神経科学分野全体のイノベーションを加速する可能性があります。
特に日本では、超高齢社会の進行とともにパーキンソン病患者数の増加が予想されており、アクセシブルな治療選択肢の提供は社会的な意義が極めて大きいといえます。既存薬物の活用により、新薬開発に比べて大幅なコスト削減と開発期間短縮が実現できれば、医療経済的な観点からも重要な意味を持つでしょう。
【用語解説】
アンブロキソール
1979年から欧州で使用されている去痰薬の有効成分。気道粘膜の潤滑油の役割を担う肺サーファクタントの産生を促進し、痰を出しやすくする作用がある。
パーキンソン病認知症
パーキンソン病の進行に伴って現れる認知機能障害。記憶、注意力、実行機能などの低下が特徴で、患者の約30-40%に発症する。
神経精神症状
パーキンソン病患者に現れる精神的・行動的症状。妄想、幻覚、不安、易怒性、無関心、異常運動活動などが含まれる。
GBA1遺伝子
グルコセレブロシダーゼ(GCase)酵素をコードする遺伝子。変異があるとパーキンソン病発症リスクが高まり、より重篤な症状を示すことが多い。
グルコセレブロシダーゼ(GCase)
細胞内のリソソームに存在する酵素。この酵素の活性低下は脳内タンパク質凝集の増加につながり、パーキンソン病の病理と関連している。
レビー小体
パーキンソン病の特徴的な病理所見。αシヌクレインタンパク質が凝集して形成される細胞内封入体で、神経細胞死の原因となる。
血液脳関門
脳と血液の間にある選択的な透過性バリア。アンブロキソールはこの関門を容易に通過できるため、脳内での治療効果が期待される。
第2相臨床試験
新薬開発の段階の一つ。安全性が確認された後、有効性を評価するために実施される中規模の臨床試験。
プラセボ対照試験
治療効果を客観的に評価するため、実薬群と偽薬群を比較する臨床試験の手法。
ドラッグリポジショニング
既存の承認薬を新たな疾患の治療に応用する創薬手法。開発期間とコストの大幅な削減が可能。
【参考リンク】
ウェスタン大学 – 神経科学部門(外部)
カナダのウェスタン大学医学部神経科学部門の公式サイト。スティーブン・パスターナック博士の研究活動について詳細情報を提供。
Cure Parkinson’s – ASPro-PD試験(外部)
英国のパーキンソン病研究支援団体による公式サイト。アンブロキソールの第3相臨床試験の詳細情報を掲載。
協和キリン株式会社(外部)
アンブロキソール塩酸塩の神経型ゴーシェ病を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相オープン試験を実施している日本の製薬会社。
欧州医薬品庁(EMA)- アンブロキソール安全性情報(外部)
欧州医薬品庁によるアンブロキソール含有医薬品の安全性に関する公式情報。アレルギー反応リスクを詳細記載。
【参考記事】
第2相無作為化二重盲検プラセボ対照試験 – JST機械翻訳(外部)
パスターナック博士らによるアンブロキソールの第2相臨床試験に関する日本語文献情報。薬物動態や認知転帰を記載。
パーキンソン病認知症に対する治療:無作為化臨床試験(外部)
アンブロキソールがパーキンソン病認知症患者において安全かつ忍容性があることを報告する日本語解説記事。
A Clinical Trial to Demonstrate Clinical Efficacy of Ambroxol in Lewy Body Disease(外部)
レビー小体病患者180名を対象としたアンブロキソールの第2相臨床試験情報。認知機能への効果を評価。
【編集部後記】
身近な咳止め薬が、まさかパーキンソン病の治療に役立つ可能性があるなんて驚きませんか?私たちの薬箱にある薬が、実は未知の力を秘めているかもしれません。皆さんは、ご自身やご家族が普段使っている薬について、どこまでご存じでしょうか?今回のアンブロキソールのように、既存の薬物が新たな用途で注目される「ドラッグリポジショニング」は、医療費削減や開発期間短縮の観点からも重要な分野です。もしかすると、今この瞬間も世界中の研究者が、私たちの身の回りにある薬の新しい可能性を探っているのかもしれません。皆さんは、どんな薬に隠された力があると思いますか?一緒に未来の医療について考えてみませんか?