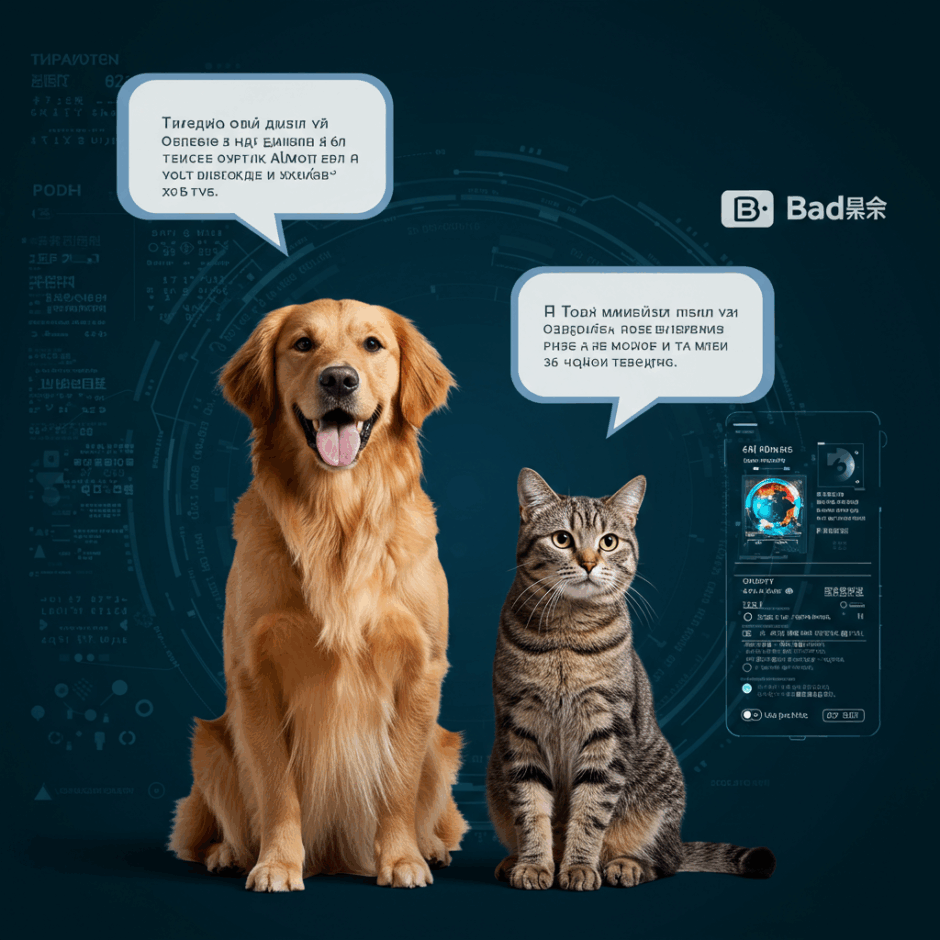中国の大手テクノロジー企業Baiduが、動物の鳴き声や行動を人間の言語に翻訳するAIシステムの特許を申請し、この特許が2025年5月6日に中国国家知識産権局によって公開された。
このシステムは、動物の発声、行動パターン、生理学的信号などのデータを収集・分析し、AIを使って動物の感情状態を認識する仕組みだ。認識された感情状態は意味のある情報としてマッピングされ、人間の言語に翻訳されることを目指している。
Baiduによれば、このシステムにより「動物と人間のより深い感情的なコミュニケーションと理解」が可能になり、異種間コミュニケーションの精度と効率が向上するとしている。
この技術はまだ研究段階にあり、Baiduの広報担当者は「特許出願に多くの関心が寄せられている」としながらも、製品化の時期については明言していない。
Baiduは2022年にOpenAIのChatGPTが登場して以降、AIへの投資を強化している企業の一つであり、2025年4月25日には最新のAIモデル「Ernie 4.5 Turbo」と「ERNIE X1 Turbo」をリリースしたばかりだ。
動物のコミュニケーションを解読する試みは他にも存在する。例えば、2020年から統計分析とAIを使ってマッコウクジラのコミュニケーション方法を研究している「Project CETI(Cetacean Translation Initiative)」や、LinkedInの共同創設者リード・ホフマンの支援を受けて2017年に設立された非営利組織「Earth Species Project」なども同様の研究を進めている。
この特許公開のニュースは中国のソーシャルメディアで話題となり、多くのユーザーがペットとのコミュニケーション向上に期待を寄せる一方で、「実際のアプリケーションでどのように機能するかを見る必要がある」と慎重な意見も出ている。
References:
 Can AI help you talk to your pet? China’s Baidu wants to turn barks and meows into human language
Can AI help you talk to your pet? China’s Baidu wants to turn barks and meows into human language
【編集部解説】
Baiduの動物翻訳AI特許申請に関する報道について、複数の信頼性の高いソースを確認したところ、Economic Times記事の内容は概ね正確ですが、いくつかの点で補足説明が必要です。
まず、Baiduの特許申請は2024年12月に行われ、2025年5月6日に中国国家知識産権局によって公開されたものです。これは特許が「承認された」わけではなく、「公開された」段階であることに注意が必要です。特許審査のプロセスは最短でも1年程度かかるとされています。
この技術は、単に動物の鳴き声を翻訳するだけでなく、より包括的なアプローチを取っています。具体的には、音声だけでなく、体の動き、行動パターン、心拍数などの生物学的信号も分析対象としており、マルチモーダルな分析を行うことで精度向上を目指しています。
また、このシステムには学習メカニズムが組み込まれており、動物の入力が既存データと一致しない場合、研究者が手動でラベル付けし、モデルを再トレーニングして精度を向上させる仕組みになっています。これは継続的な改善を可能にする重要な特徴です。
Baiduはこの分野の先駆者というわけではありません。動物コミュニケーションの解読は長年研究されてきた分野で、特にProject CETI(Cetacean Translation Initiative)は2020年からAIと統計分析を組み合わせてマッコウクジラのコミュニケーション方法を研究しています。また、LinkedInの共同創設者リード・ホフマンが支援するEarth Species Projectも2017年から同様の研究を進めています。
Baiduがこの分野に参入する背景には、AIへの大規模投資戦略があります。同社は2025年4月25日に最新のAIモデル「ERNIE 4.5 Turbo」と「ERNIE X1 Turbo」をリリースしたばかりで、これらのモデルはマルチモーダル機能を強化しており、動物コミュニケーション解読への応用も視野に入れていると考えられます。
興味深いことに、Baiduのロゴには犬の足跡が使われており、同社が動物とのコミュニケーションに特別な関心を持っていることを象徴しているようにも見えます。
この技術が実用化された場合、ペットケアや獣医療の分野に革命をもたらす可能性があります。例えば、ペットの健康状態や感情をより正確に把握できるようになれば、早期の病気発見や適切なケアが可能になるでしょう。また、野生動物保護や生態系研究においても、動物の行動や感情をより深く理解することで、より効果的な保全策を講じることができるかもしれません。
一方で、この技術には課題も存在します。動物の発声や行動は種によって大きく異なり、同じ種の中でも個体差があります。また、人間の言語概念を動物のコミュニケーションに当てはめることの妥当性についても議論があります。動物は人間とは異なる認知構造を持っており、その「言語」を人間の言語体系に翻訳することには本質的な限界があるかもしれません。
また、このような技術の商業化には倫理的な問題も伴います。ペットの「言葉」を理解できるという謳い文句で販売される製品が、実際には科学的根拠に乏しい場合、消費者の誤解や失望を招く恐れがあります。
現時点では、Baiduの技術はまだ研究段階にあり、実用化までには時間がかかると見られています。しかし、AIの急速な進化を考えると、近い将来、私たちとペットとのコミュニケーションの方法が大きく変わる可能性は十分にあるでしょう。
innovaTopia編集部としては、この技術の進展を注視しつつ、科学的根拠に基づいた冷静な評価を続けていきたいと考えています。テクノロジーの進化が人間と動物の関係性をどのように変えていくのか、その可能性と限界について、今後も読者の皆様に最新情報をお届けしていきます。
【用語解説】
Baidu(百度):
中国最大の検索エンジン企業で、2000年に李彦宏(Robin Li)と徐勇(Eric Xu)によって創立された。中国版Googleとも呼ばれ、AI技術開発にも積極的に投資している。特徴的なロゴには犬の足跡が使われており、動物とのつながりを象徴している。
ERNIE(Enhanced Representation through Knowledge Integration):
Baiduが開発した大規模言語モデル。知識統合による表現強化を特徴とし、2019年に初めて発表された。現在はERNIE 4.5 TurboやERNIE X1 Turboなど複数のバージョンが存在する。
Earth Species Project:
動物のコミュニケーションを解読・翻訳することを目的とした非営利団体。LinkedInの共同創設者リード・ホフマンなどの支援を受けている。
Project CETI(Cetacean Translation Initiative):
マッコウクジラのコミュニケーション方法を研究するプロジェクト。ハーバード大学、MIT、インペリアル・カレッジなどの研究者が参加している。
マルチモーダルAI:
複数の種類のデータ(テキスト、画像、音声など)を同時に処理できるAIモデル。Baiduの動物翻訳AIも、音声だけでなく動物の行動パターンや生理的信号も分析する。
【参考リンク】
Baidu(百度)公式サイト(外部)
中国最大の検索エンジンを提供する企業の公式サイト。中国語のみの対応。
Baidu Research(外部)
Baiduの研究開発部門のサイト。ERNIEなどのAI技術に関する情報が掲載されている。
Earth Species Project(外部)
動物のコミュニケーションを解読する非営利団体の公式サイト。
Project CETI(外部)
マッコウクジラのコミュニケーション研究プロジェクトの公式サイト。
Baidu Japan(バイドゥ株式会社)(外部)
Baiduの日本法人。日本企業の中国向けマーケティング支援や日本語キーボードアプリ「Simeji」を提供。
【参考動画】
【編集部後記】
ペットの気持ちを言葉で理解できたら、どんな会話をしてみたいですか?単に「お腹すいた」だけでなく、「今日は少し寂しかった」「あの犬が怖かった」といった複雑な感情も伝えてくれるかもしれません。もしご自宅でペットを飼われている方は、今日の帰り道、愛するペットの仕草や鳴き声をいつもより少し注意深く観察してみてはいかがでしょう。そこには私たちがまだ気づいていないメッセージが隠されているかもしれません。AIが動物の言葉を解読する日は、思ったより近いのかもしれませんね。