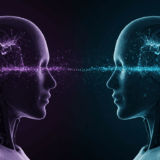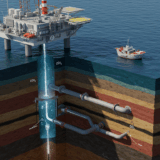NASAは2025年8月25日にTOMEX+観測ロケットミッションの打ち上げを予定している。打ち上げ時間は東部夏時間午後10時から午前3時までの打ち上げウィンドウで実施される。打ち上げ場所はバージニア州のNASAワロップス飛行施設である。
このミッションの主要目的は電離層と宇宙天気に関するデータ収集である。電離層は衛星や無線システムの通信妨害を引き起こす電気的に帯電した大気領域で、太陽風などの要因がこの領域に与える影響を分析する。また熱圏の研究も実施し、地表から約50マイル(80km)から400マイル(640km)の高度に位置するこの大気層の組成、密度、挙動を調査する。
観測ロケットは地球上層大気に機器を運び、短時間飛行後に地表に戻る設計となっている。軌道ミッションとは異なり宇宙空間には入らない。TOMEX+ミッションではカメラ、分光計、温度・圧力・イオン密度測定機器などの科学的ペイロードを搭載する。NASAは打ち上げ期間中にリアルタイム更新を提供し、一般の人々がウェブサイトを通じてミッションを追跡できるようにする。
From:  NASA to Launch Groundbreaking TOMEX+ Rocket Mission for Space Weather Insights
NASA to Launch Groundbreaking TOMEX+ Rocket Mission for Space Weather Insights
【編集部解説】
私たちの暮らしはいま、電離層というわずか数十マイルの薄い大気層に支えられていると言っても過言ではありません。スマートフォンでGPSナビを使い、衛星放送でニュースを見て、国際電話をかける。これらすべてが、地上50〜400マイル上空の電離層を電波が通過することで成り立っているからです。
TOMEX+ミッションの真の価値は、この「見えないインフラ」の動きを可視化することにあります。原記事では「3基のロケットを1分間隔で打ち上げ、蛍光トレーサーとレーザー技術を組み合わせて大気の乱流を3次元的にマッピングする」という詳細な実験手法が説明されています。これは単なる科学実験ではなく、現代社会のデジタルライフラインを守るための実用研究なのです。
興味深いのは、この実験が高度85〜105kmのメソポーズ領域(約53〜65マイル)で「原子ナトリウム層」を利用している点です。宇宙から降り注ぐ流星が燃え尽きる際に残したナトリウム原子を、特殊なレーザーで光らせて大気の動きを追跡するという巧妙な仕組みです。まさに宇宙の「ちり」を科学的な道具として活用する巧妙な発想といえるでしょう。
このタイミングでNASAがこうした研究を急ぐ背景には、太陽活動の活発化があります。現在は11年周期の太陽活動サイクルの極大期に近づいており、太陽フレアや磁気嵐による通信障害のリスクが高まっています。実際、激しい宇宙天気は衛星の機能停止、電力網の障害、GPS精度の悪化を引き起こす可能性があります。
なお、当初8月18日開始予定だったTOMEX+ミッションは、ハリケーン・エリンの影響による天候不良と海況悪化により複数回延期され、8月25日の打ち上げとなりました。
一方で、この研究が開拓する未来は明るいものです。宇宙天気の予測精度が向上すれば、衛星運用者は事前に機器を保護モードに切り替え、航空会社は極地航路を避け、電力会社は送電システムを調整できるようになります。これは「宇宙天気予報」という新しいサービス分野の創出も意味しています。
長期的には、この技術は月や火星探査ミッションの安全性向上にも貢献するでしょう。宇宙飛行士の放射線被曝リスクを軽減し、より安全な宇宙進出への道筋をつけることになります。
TOMEX+が描く未来は、宇宙天気を「予測不可能な脅威」から「管理可能なリスク」へと変える、人類の宇宙活動にとって重要な転換点なのです。
【用語解説】
TOMEX+(Turbulent Oxygen Mixing Experiment Plus)
大気の最上層部における酸素と窒素の乱流混合現象を調査するNASAの観測ロケットミッション。2000年に実施された初代TOMEXミッションの発展版である。
観測ロケット(サウンディングロケット)
地球の上層大気に科学機器を運び、軌道に入らずに弾道飛行で短時間のデータ収集を行う研究用ロケット。飛行時間は通常5〜20分程度で、衛星より低コストで実験が可能である。
電離層
地表から約50〜400マイル(80〜640km)上空に位置する大気層で、太陽紫外線によって大気分子がイオン化された電気的に帯電した領域。GPS、衛星通信、短波ラジオなどの電波伝播に大きく影響する。
熱圏
地表から約50マイル(80km)から400マイル(640km)上空に広がる大気層。オーロラが発生し、多くの衛星が軌道する領域である。温度は高度とともに上昇する。
メソポーズ
中間圏と熱圏の境界にあたる高度85〜105km(53〜65マイル)付近の大気層。地球大気で最も温度が低く、約マイナス148度(マイナス100℃)に達する。夜光雲が形成される場所でもある。
ナトリウム層
高度約90km付近に存在する原子ナトリウムの層。宇宙から降り注ぐ微小な流星が大気中で燃え尽きる際に残されたナトリウム原子によって形成される。
宇宙天気
太陽風、太陽フレア、磁気嵐などの太陽活動が地球の磁場や電離層に与える影響のこと。人工衛星の故障、通信障害、電力系統の異常などを引き起こす可能性がある。
【参考リンク】
NASA ワロップス飛行施設(外部)
NASAの弾道および小型軌道ミッションの主要拠点として1945年設立
NASA 観測ロケットプログラム(外部)
40年以上にわたり年間約20回のミッションを実施する宇宙科学研究プログラム
NASA ワロップス飛行施設 観測ロケットプログラム事務所(外部)
地球科学、太陽物理学、天体物理学研究を支援する運営組織
【参考記事】
NASA’s TOMEX+ Rocket to Track Turbulence at Edge of Space(外部)
TOMEX+ミッションの詳細な技術仕様と3次元マッピング実験手法を解説
NASA Sounding Rocket Mission Targeting Aug. 25 Launch Attempt(外部)
2025年8月25日の打ち上げスケジュールと打ち上げウィンドウの公式発表
How space weather affects technology(外部)
宇宙天気が現代技術に与える具体的影響と被害事例、対策を分析
Space Weather Prediction: A Future Powered by Explainable AI(外部)
AI技術を活用した宇宙天気予測の将来展望と予測精度向上の重要性
Embry-Riddle Researchers Launch Rockets for a Deeper Look(外部)
電離層研究の学術的背景と通信障害メカニズムを詳説する大学研究
【編集部後記】
今夜バージニアの空に打ち上がったTOMEX+の光跡は、私たちの日常を支える見えないインフラを解明する第一歩です。スマートフォンのGPSが時々不正確になったり、衛星放送が乱れたりする現象の背景には、はるか上空の電離層の動きが関わっています。日本でも情報通信研究機構(NICT)が24時間体制で宇宙天気予報業務を行っており、富士通やJAXAが説明可能なAIを活用した次世代予報システムの開発を進めています。
皆さんは普段、宇宙の天気を意識されたことはありますか?これからの時代、地上の天気予報と同じように宇宙天気予報が当たり前になるかもしれません。
私たちの暮らしを支える宇宙インフラについて、一緒に考えてみませんか?