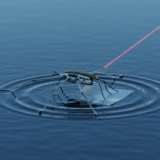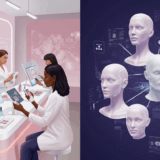スタディメーター株式会社は、同社が運営する高校生・大学生によるビジネスコミュニティ「First off Projects」が開発した「未来の教科書」を、2025年10月3日より日本科学未来館1階の「Tokyo Mirai Park」で展示開始した。展示期間は2026年1月末までを予定している。未来の教科書は、教科書のタイトルを入力するだけでAIが教科書を生成するWebサービスで、無料で利用できる。今回の展示に合わせて、動画生成・PDF出力・参考文献表示という3つの新機能を追加した。動画は1分程度で、スクリプトやナレーション音声はAIが作成し、挿絵にはストック画像を利用することで生成を高速化している。PDF出力機能では、A4両面1ページで印刷できるPDFを自動出力し、二つ折りにすると小冊子のように読める仕様となっている。参考文献収集機能は、2024年の初期リリース当初から指摘されていたハルシネーションへの懸念に対応するため、生成の元になった情報を表示する。開発チームは初期版を高校生時代に手掛けた学生が大学生となり、新たに参画した高校生とともに機能開発に取り組み、3つの新機能を企画から開発まで1カ月で実現した。
From:  タイトルを入力するだけでAIが教科書と解説動画を生成 – 高校生の開発した「未来の教科書」が日本科学未来館のTokyo Mirai Parkで展示開始!
タイトルを入力するだけでAIが教科書と解説動画を生成 – 高校生の開発した「未来の教科書」が日本科学未来館のTokyo Mirai Parkで展示開始!
【編集部解説】
このプロジェクトが示しているのは、生成AIを活用した教育の民主化という大きな潮流です。タイトルを入力するだけで教科書と解説動画が生成されるという体験は、学びたい内容を即座に形にできる時代の到来を象徴しています。
特筆すべきは、開発者が高校生と大学生である点です。従来であれば専門的な開発スキルが必要とされた領域で、生成AIを活用しながら1カ月で3つの新機能を実装したという事実は、技術の進化が創造の敷居を劇的に下げていることを物語っています。
今回追加された参考文献表示機能は、生成AIの最大の課題であるハルシネーション(虚偽情報の生成)に対する実用的なアプローチとして注目に値します。情報の出典を明示することで、利用者自身が内容の信頼性を検証できる仕組みは、AI時代のリテラシー教育にも通じる設計思想といえるでしょう。
開発チームが「なぜ人は本屋に行くのか」という問いから出発した点も興味深い視点です。情報過多の時代における学びの体験設計として、本屋での立ち読みという偶発的な発見の楽しさをデジタル空間で再現しようとする試みは、単なる効率化を超えた価値提案を含んでいます。
一方で、AIが生成する教科書は汎用的な基礎知識に特化し、深い考察や個性的な視点は紙の本に委ねるという割り切りも現実的です。デジタルと紙のすみ分けを明確にすることで、それぞれのメディアが持つ本来の強みを活かす教育環境の構築を目指している点は、テクノロジーと人間性の共存を考える上で示唆に富んでいます。
日本科学未来館での展示では、毎日異なるテーマの冊子が生成され、来場者同士が「いま学びたいテーマ」を共有できる仕組みになっています。この物理空間とデジタル生成の融合は、AI時代の新しい学びのコミュニティのあり方を提示する実験といえるでしょう。
【用語解説】
ハルシネーション
生成AIが事実に基づかない情報や虚偽の内容を、あたかも真実であるかのように出力してしまう現象を指す。AI特有の課題として知られ、教育分野での活用において信頼性確保の重要な論点となっている。
First off Projects
スタディメーター株式会社が運営する高校生と大学生のためのビジネスコミュニティ。メンバーは資金や学習機会の援助を受け、関心に基づいたサービス開発や学習レポート作成を通じて、新技術の知見や事業創出事例を企業に還元する研究機関的な役割を担っている。
Tokyo Mirai Park
日本科学未来館1階に設置された展示スペース。未来志向のプロジェクトやテクノロジーを紹介する場として、さまざまな先端技術やサービスの展示を行っている。
【参考リンク】
未来の教科書(公式サイト)(外部)
タイトルを入力するだけでAIが教科書と解説動画を生成するWebサービス。無料で利用でき、動画生成、PDF出力、参考文献表示の機能を搭載している。
日本科学未来館 Tokyo Mirai Park(外部)
日本科学未来館1階の展示スペース。先端技術やイノベーションプロジェクトを紹介し、来場者が未来の技術を体験できる場を提供している。
【参考記事】
タイトルを入力するだけでAIが教科書と解説動画を生成 – 高校生の開発した「未来の教科書」が日本科学未来館のTokyo Mirai Parkで展示開始!(外部)
スタディメーター株式会社が発表したプレスリリース。高校生・大学生によるビジネスコミュニティ「First off Projects」が開発した「未来の教科書」が2025年10月3日より日本科学未来館で展示を開始した。
【編集部後記】
もし皆さんが「教科書」を自由に作れるとしたら、どんなタイトルをつけてみたいですか?「未来の教科書」は、そんな問いかけを私たちに投げかけてくれます。高校生たちが生成AIを使いこなして1カ月で機能を実装したという事実は、技術の民主化がどこまで進んでいるかを示しています。実際にサイトを訪れて、気になるテーマで教科書を生成してみると、AIと学びの新しい関係性が見えてくるかもしれません。日本科学未来館での展示では、他の来場者が選んだテーマも見られるそうです。偶然の出会いから生まれる学びの楽しさ、皆さんはどう感じられるでしょうか。