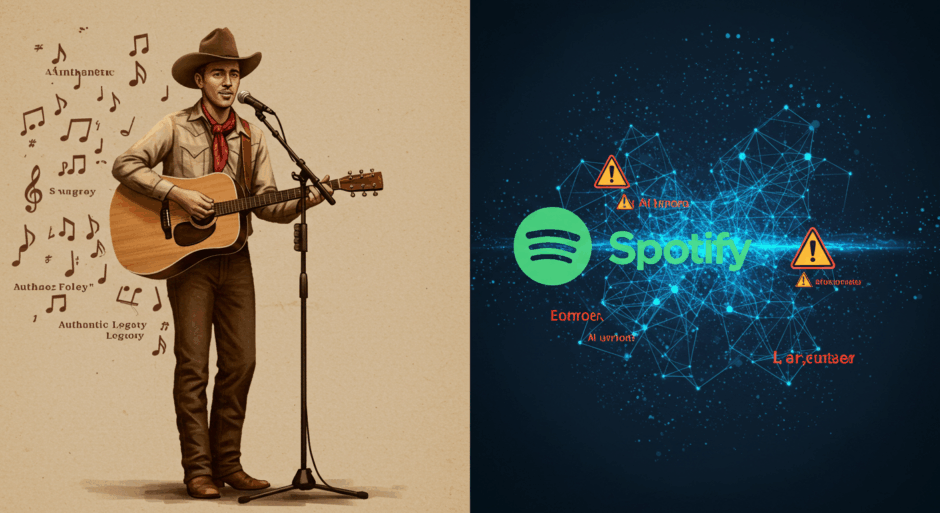2025年7月下旬、Spotifyは1989年に殺害された故カントリーシンガーBlaze Foleyの公式プロフィールにAI生成楽曲「Together」が無許可でアップロードされた問題で、同楽曲を削除した。楽曲は「Syntax Error」名義でTikTok傘下の音楽配信サービスSoundOnを通じて配信された。Foleyの楽曲配信を管理するLost Art RecordsのCraig McDonaldは「この楽曲はBlazeではなく、彼のスタイルとも全く異なる」と404 Mediaに証言した。同様の事例はカントリーシンガーGuy Clarkでも発生した。Spotifyの広報担当者はCNETに対し「偽装コンテンツポリシーに違反する」として削除を確認し、配信業者への監視強化を表明した。この問題は人気のAIバンドThe Velvet Sundownなど、AI生成音楽の拡大を背景とする。
From: Spotify Takes Down Fake AI Song Credited to Famous Country Singer Who’s Been Dead for Years
Spotify Takes Down Fake AI Song Credited to Famous Country Singer Who’s Been Dead for Years
【編集部解説】
今回のSpotifyでのAI楽曲偽装事件は、音楽業界におけるAI技術の急速な普及と、それに追いつかないプラットフォームの管理体制を浮き彫りにした象徴的な出来事です。この問題を技術的・産業的な視点から詳しく解説いたします。
AI音楽生成技術の現状と課題
現在、SunoやUdioといったAI音楽生成プラットフォームでは、テキストプロンプトだけで楽曲を制作することが可能になっています。これらの技術は既存楽曲を学習データとして活用しており、特定のアーティストのスタイルを模倣することも技術的には容易です。
ただし、今回の「Together」のように完全に異なるアーティストの名前で配信することは、技術的な問題というよりも意図的な詐欺行為に該当します。問題の本質は、AI技術の悪用と配信プラットフォームの本人確認システムの脆弱性にあると言えるでしょう。
配信プラットフォームの構造的問題
Spotifyを含む多くのストリーミングサービスは、SoundOnやCD Baby、DistroKidなどの第三者配信業者を通じて楽曲を受け付けています。この多層構造が、今回のような偽装を可能にしてしまいました。
特に注目すべきは、Lost Art RecordsのCraig McDonald氏が関与したコメントです。これは、正規の権利者でさえプラットフォームの仕組みを完全に把握していない現状を示しています。
音楽業界への経済的影響
AI生成楽曲の無制限な拡散は、音楽業界の収益構造に深刻な影響を与える可能性があります。音楽業界全体でAI生成楽曲の流入が急増しており、人間のアーティストにとって、これらのAI楽曲はストリーミング再生数を巡る競合相手となっています。
すでに微少なロイヤリティをさらに希薄化させる要因となっており、音楽クリエイターの経済的基盤を脅かす可能性があります。
法的・倫理的な複合問題
この事件は単純な著作権侵害を超えた複合的な法的問題を提起しています。死去したアーティストの人格権の侵害、商標権の悪用、そして消費者に対する詐欺的行為が同時に発生している状況です。
また、AI学習データとして使用された楽曲の著作権者も、間接的な権利侵害の被害者となる可能性があります。現在、主要レコードレーベルがSunoやUdioに対して集団訴訟を起こしており、業界全体での法的対応が進んでいます。
プラットフォームの対応策と限界
Spotifyは今回の件を受けて「偽装コンテンツポリシー違反」として楽曲を削除しましたが、根本的な解決策は示していません。実際の判定基準は曖昧なままとなっています。
一方、他のプラットフォームではAI検出アルゴリズムの開発や、AI生成楽曲の明確な表示を始めているところもあります。この技術的なアプローチの差が、今後のプラットフォーム競争に影響を与える可能性があります。
今後の展望と規制の方向性
音楽業界では、AI企業が創作物を無許可で学習に使用し、人間のアーティストと直接競合している現状への懸念が高まっています。新たな保護制度の必要性が訴えられている状況です。
技術的には、ブロックチェーンを活用した楽曲の出自証明システムや、生体認証を組み合わせたアーティスト認証システムの導入が検討されています。ただし、これらの実装には業界全体での標準化が不可欠となります。
長期的な視点では、AI音楽生成技術そのものは創作支援ツールとして有用であり、完全な禁止ではなく適切な規制とラベリングによる共存が現実的な解決策となるでしょう。今回の事件は、その規制枠組み構築の緊急性を改めて浮き彫りにした重要な転換点と位置づけられます。
【用語解説】
AI音楽生成技術
テキストプロンプトや音声サンプルを基に、人工知能が自動的に楽曲を作成する技術。SunoやUdioなどのプラットフォームが代表的である。
ストリーミングプラットフォーム
インターネット経由で音楽を配信するサービス。ユーザーは楽曲をダウンロードせずに、リアルタイムで音楽を再生できる。
音楽配信業者(ディストリビューター)
アーティストの楽曲を各種ストリーミングサービスに代理配信する企業。CD Baby、DistroKid、TuneCoreなどが存在する。
偽装コンテンツポリシー
プラットフォームが設定する規約で、他者になりすましたり、誤解を招く形での楽曲配信を禁止する内容。
アウトロー・カントリー
1970年代に登場したカントリーミュージックのサブジャンル。既存の商業的カントリーに反発し、より自由で反骨精神に満ちた音楽性を特徴とする。
人格権
個人の名誉や氏名、肖像などの人格的利益を保護する権利。死後も一定期間保護される場合がある。
【参考リンク】
Spotify(外部)
世界最大級の音楽ストリーミングサービス。月間アクティブユーザー数は5億人を超え、楽曲数は1億曲以上を誇る。
SoundOn(外部)
TikTokが2022年に開始した音楽配信・マーケティングプラットフォーム。アーティストが直接TikTokや他のストリーミングサービスに楽曲をアップロードできる。
Lost Art Records(外部)
テキサス州オースティンを拠点とするレコードレーベル。故Blaze Foleyの楽曲カタログを管理している。
404 Media(外部)
技術とメディアの交差点に焦点を当てた独立系ニュースサイト。今回のSpotify AI楽曲問題を最初に報道した。
【参考記事】
Spotify Publishes AI-Generated Songs From Dead Artists Without Permission(外部)
Blaze FoleyとGuy Clarkの両方のケースを分析し、Lost Art RecordsのCraig McDonald氏のコメントを含む包括的な報道。
The Velvet Sundown: Inside the bizarre truth about ‘popular’ band(外部)
人気のAIバンドThe Velvet SundownがAI生成であることを公式に認めた経緯と、音楽業界への影響について報じた記事。
【編集部後記】
今回のSpotifyでのAI楽曲偽装事件を通じて、私たち一人ひとりが音楽の未来について考える大切な時期に来ていると感じています。皆さんは普段、お気に入りのアーティストの新曲を聴く時、それが本物かどうかを疑うことはありますか?
AI技術の進歩は確実に私たちの生活を豊かにしてくれる一方で、今回のような問題も生み出しています。この変化の波の中で、私たちリスナーはどのような姿勢で音楽と向き合っていけばよいのでしょうか。また、アーティストを応援したい気持ちと、新しい技術への興味の間で、どうバランスを取っていけばよいでしょうか。
ぜひ皆さんのご意見や体験を、SNSなどでシェアしていただけると嬉しいです。
一緒にこの新しい時代の音楽について考えていきましょう。