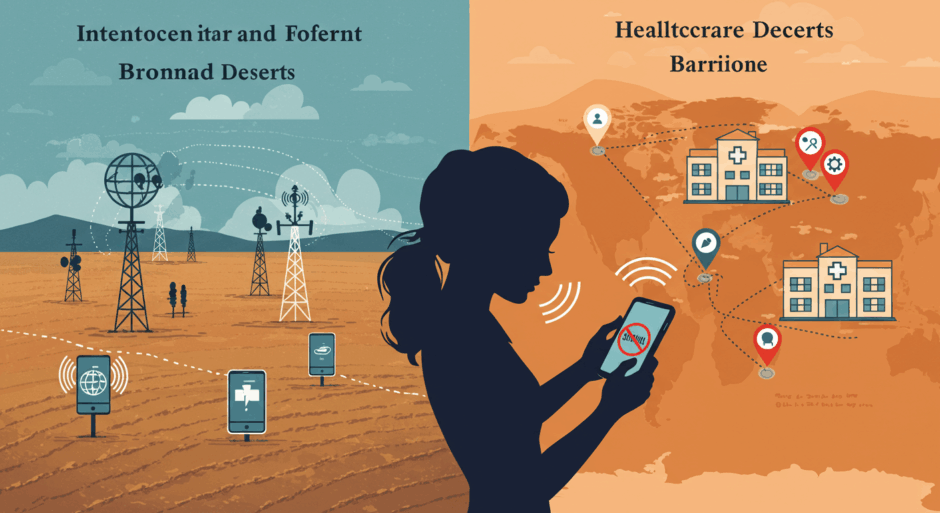全米女性法センター(NWLC)は2025年4月、新たな調査レポートを発表した。 同センターのSara Javaid氏とLexi Rummel氏によるこの報告書によると、米国の約半数の郡が、最寄りの中絶ケア施設まで100マイル以上の距離がある「中絶不毛地帯」となっている。
中絶不毛地帯の53%は妊娠ケア不毛地帯でもある。ブロードバンド不毛地帯と中絶ケア不毛地帯の両方に住む女性は74万人以上で、その約3分の1が有色人種女性である。ブロードバンド不毛地帯は住民の半数以上が100Mbpsダウン/20Mbpsアップの速度にアクセスできない郡で、米国の郡の10分の1がこれに該当する。
2024年のピュー研究センター調査では年収3万ドル未満成人の57%がインターネット契約を持つのに対し、年収10万ドル以上では95%が契約している。ドブス対ジャクソン判決後、乳児死亡率が増加した。手頃なコネクティビティプログラムは2024年6月に終了し、低所得家庭の月額インターネット料金を30ドル割引していた。
From:  Mapping the Margins: The Internet’s Invisible Hand in Reproductive Care
Mapping the Margins: The Internet’s Invisible Hand in Reproductive Care
【編集部解説】
米国では「中絶不毛地帯」と「ブロードバンド不毛地帯」が重なる地域に74万人以上の女性が暮らしています。近隣に中絶施設がなく、しかも高速インターネット環境も整っていないため、オンライン診療や情報取得という”最後の手段”まで奪われる状況です。テレヘルスが一般化した2020年代半ばにあって、これは看過できない二重のアクセス格差です。
中絶不毛地帯は「最寄りの中絶クリニックまで100マイル(約160km)超」と定義されますが、報告書の著者は「公共交通機関が乏しければ25マイルでも実質的な不毛地帯になり得る」と警鐘を鳴らしています。さらに、FCCが2022年時点で示した「下り100Mbps/上り20Mbps未満の世帯が半数を超える郡」をブロードバンド不毛地帯とする基準は、既に実態を過小評価しているとの指摘もあります。地域自立研究所コミュニティブロードバンドネットワークイニシアティブのディレクターChristopher Mitchell氏は「実数は少なくとも4倍」と推計しており、数字以上に深刻と見るべきです。
価格面のハードルも大きいです。2024年調査では年収3万ドル未満の成人で固定回線契約率が57%にとどまり、10万ドル以上の95%と大差があります。低所得世帯を月額30ドル補助してきたACP(Affordable Connectivity Program)が2024年6月に終了した影響で、利用者の解約が加速したとの報告も出ています。
テクノロジー面では、州がISPに月15ドルの低料金プランを義務付けるニューヨークの取り組みや、BEAD(Broadband, Equity, Access and Deployment)基金による「非敷設」支援が注目されています。図書館や病院などアンカー拠点への投資を認めるBEADの柔軟運用が進めば、遠隔医療の受け皿が地域につくられ、産婦人科医不足の補完策になり得ます。
一方で、リプロダクティブ・ヘルス関連サイトへのアクセス履歴が州当局の捜査対象となるリスクも無視できません。通信各社がメタデータを保持する期間や、州境を越えた医療行為をめぐる法的グレーゾーンなど、プライバシーと表現の自由の両面で新たな規制議論が高まる可能性があります。
長期的には、通信インフラの整備だけでなく「利用できる価格・端末・デジタルリテラシー」をワンセットで支援しない限り、医療格差は縮まりません。テクノロジーが本来持つ包摂力を最大化するには、接続の”量”だけでなく”質”――すなわち誰が、どのように、安心して使えるか――を測る指標づくりが不可欠です。
本件は、インフラ政策がリプロダクティブ・ライツという極めて私的な領域に直結することを示す好例です。読者の皆さまが技術者として、あるいはプロダクト企画の立場で関与する際は、「接続そのものが医療アクセスである」という視点を持つことで、新たなサービス機会が見えてくるはずです。
【用語解説】
ドブス対ジャクソン判決(Dobbs v. Jackson)
2022年6月24日に米連邦最高裁判所が下した判決で、1973年のロー対ウェイド判決を覆し、中絶の権利を連邦憲法上の権利として認めないとした。各州が中絶法を独自に決定できるようになった。
ACP(Affordable Connectivity Program)
2021年に開始され2024年6月に終了した米国の低所得世帯向けインターネット料金補助プログラム。月額30ドルの割引を提供していた。
【参考リンク】
全米女性法センター(National Women’s Law Center)(外部)
1972年設立の非営利組織。女性とLGBTQの権利、ジェンダー正義実現に向けた政策提言・訴訟・調査研究を行う。
ベントンブロードバンド・社会研究所(外部)
1981年設立の非営利研究機関。ブロードバンドアクセス格差解消とテクノロジーの社会的影響を研究。
コミュニティブロードバンドネットワークイニシアティブ(外部)
地域自立研究所運営。コミュニティ主導のブロードバンド整備支援と地域レベルでのアクセス改善に取り組む。
Ookla Speedtest(外部)
2006年設立のインターネット速度測定サービス。世界中で毎日1100万回以上のテスト実施。
ピュー研究センター(Pew Research Center)(外部)
無党派の調査研究機関。インターネット利用状況、デジタル格差の定期的な調査を実施。
【参考記事】
U.S. infant mortality increased 7% in months following Dobbs(外部)
オハイオ州立大学の研究で、ドブス判決後7-14か月間で米国の乳児死亡率が7%増加したことが判明。
Americans’ Use of Mobile Technology and Home Broadband(外部)
ピュー研究センターによる2024年調査。年収3万ドル未満成人の57%のみがインターネット契約を保有。
【編集部後記】
今回の記事を通して、テクノロジーが単なる便利ツールではなく、人の生命に関わるライフラインであることを改めて感じました。皆さんの住む地域では、高速インターネットは当たり前のように使えているでしょうか?一方で、遠隔医療やデジタルヘルスの分野では、アクセス格差を解消するためにどのような技術的アプローチが有効なのでしょうか?私たちinnovaTopia編集部も、テクノロジーが真に人類の進化に寄与するための議論を、読者の皆さんと一緒に深めていければと思っています。