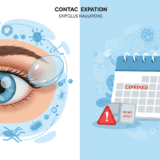外付けGPU(eGPU)の価値は技術環境の変化により複雑化している。Razerは2025年にThunderbolt 5対応のeGPUエンクロージャ「Core X V2」を発表した。
同製品は350ドルで販売され、双方向80Gbps、Bandwidth Boostモード使用時は一方向120Gbpsの帯域幅を提供する。従来モデルと異なり内蔵電源とI/Oポートが削除されており、I/O拡張を目的とするユーザーは、別途発売されたドッキングステーションを組み合わせる必要がある。PC GamerがRTX 4070 TiとRTX 4090を用いて実施したテストでは、Thunderbolt接続がOCuLink接続より約25%遅く、フレームスタッターが発生する傾向が確認された。
MinisforumのDEG1はOCuLink規格を採用した99ドルのオープンエアeGPUドックで、RTX 4080 SuperでCyberpunk 2077とReturnalがデスクトップとほぼ同等の性能を発揮すると報告されている。ASUSは2025年版ROG XG MobileでThunderbolt 5対応を実現し、従来の独自コネクタから汎用性の高い規格に移行した。eGPUは依然として70-80%のデスクトップ性能に留まり、ニッチ市場に位置している。
From:  Are external GPUs still worth it in 2025?
Are external GPUs still worth it in 2025?
【編集部解説】
eGPU市場の技術的転換点を読み解く
2025年のeGPU市場は、まさに技術的な転換期を迎えています。Thunderbolt 5の実用化により、従来の帯域幅制約が大幅に改善された一方で、ノートPC内蔵GPUの高性能化やクラウドゲーミングの普及により、eGPUの存在意義が根本的に問い直されている状況です。
インターフェース規格の競争激化
現在のeGPU市場では、Thunderbolt 5とOCuLinkという2つの異なるアプローチが競合しています。Thunderbolt 5は理論値120Gbpsの帯域幅を提供しますが、実際のGPU接続では理論値に対して制限が生じるという技術的制約があります。
一方のOCuLinkは、より直接的なPCIe接続により低遅延を実現する反面、対応デバイスが限定的という課題を抱えています。この技術競争により、ユーザーは接続方式の選択という新たな判断を迫られることになります。
コスト効率性の再評価が必要
RazerのCore X V2が350ドルで販売される一方、内蔵電源や拡張ポートを削除したことで、実質的な総コストは従来機種を上回る可能性があります。この価格設定は、eGPUの普及を阻害する要因として懸念されます。
特に注目すべきは、同等の投資額で新品のゲーミングノートPCが購入可能という現実です。これは、eGPUが真の意味での「コスト効率的なソリューション」といえるかどうかを問う重要な指摘といえるでしょう。
Apple Siliconの影響とエコシステムの変化
2025年現在、Apple Silicon MacがeGPUをサポートしていないという状況は、市場全体に大きな影響を与えています。これまでクリエイティブ分野で重要な位置を占めていたMacユーザーがeGPUを活用できないことで、市場規模の縮小が避けられない状況です。この変化により、eGPUは実質的にWindows PCおよびLinuxプラットフォームに特化した製品となり、より限定的な用途に収束していく可能性が高まっています。
クラウドコンピューティングとの競合関係
GeForce NowやXbox Cloud Gamingなどのクラウドサービスの成熟は、eGPUにとって予想以上に深刻な競合要因となっています。特に4K 60FPSでのストリーミング配信が安定化したことで、ローカルでの高性能GPU処理の必要性が相対的に低下しつつあります。
ただし、競技ゲーミングや精密な創作作業においては、遅延の問題からローカル処理の優位性は保たれており、この分野でのeGPUの価値は依然として存在します。
長期的な市場展望
2025年以降のeGPU市場は、より専門性の高いニッチ市場へと収束していくと予測されます。特にLinuxベースのミニPCやWindows携帯ゲーム機での活用が、新たな成長領域として注目されています。
また、OCuLink対応デバイスの増加により、Thunderboltに代わる新たなエコシステムが形成される可能性もあり、この動向は今後の市場競争を左右する重要な要素となるでしょう。技術革新のスピードが加速する中で、eGPUがどのような進化を遂げるかは、まさに2025年が分水嶺となりそうです。
【用語解説】
Thunderbolt 5
Intelが開発した最新の高速データ転送規格。双方向80Gbps、Bandwidth Boostモード時には一方向120Gbpsの帯域幅を提供し、従来のThunderbolt 4の2倍の性能を実現する。
OCuLink(Optical Copper Link)
PCIe信号を直接伝送するインターフェース規格。4つのPCIeレーンを使用し、eGPU接続において低遅延を実現する。主にミニPCやハンドヘルドゲーミングデバイスで採用される。
PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)
コンピュータ内部でGPUやストレージなどの拡張カードを接続するための高速バス規格。x16は16レーン、x8は8レーンを示し、レーン数が多いほど高い帯域幅を提供する。
フレームスタッター
ゲーム画面の表示が不規則に停止したり、滑らかでない動きになる現象。主に帯域幅不足やデータ転送の遅延によって発生し、ゲーム体験を著しく損なう。
【参考リンク】
Razer公式サイト(外部)
Thunderbolt 5対応のeGPUエンクロージャ「Core X V2」を販売するRazerの日本公式サイト
Intel Thunderbolt技術概要(外部)
IntelによるThunderbolt技術の公式説明ページ。最大80Gbpsの技術仕様を詳しく解説
Minisforum公式サイト(外部)
99ドルのOCuLink対応eGPUエンクロージャーDEG1の仕様と使用条件について説明
ASUS ROG公式サイト(外部)
ゲーミング向けeGPUソリューション「ROG XG Mobile」の最新情報を提供
NVIDIA GeForce NOW(外部)
NVIDIAのクラウドゲーミングサービス。GeForce RTXによる高性能ストリーミング
Xbox Cloud Gaming(外部)
Xbox Game Pass Ultimate会員向けのクラウドゲーミングサービス公式サイト
Amazon Luna(外部)
AmazonのクラウドゲーミングサービスLuna。幅広いゲームライブラリを提供
【参考記事】
State of Play: eGPUs(外部)
PC GamerによるeGPUの詳細な性能分析記事。重要なベンチマークデータを提供
Minisforum DEG1 hands-on(外部)
Digital TrendsによるMinisforum DEG1の実機レビュー記事
【編集部後記】
この記事を読まれて、皆さんはどのように感じられたでしょうか。eGPUという技術は、まさにモバイルワークと高性能コンピューティングの狭間で揺れ動く現代の象徴的な存在かもしれません。特に、リモートワークが当たり前になった今、「必要な時だけ高性能」という発想は多くの方に共感いただけるのではないでしょうか。クラウドゲーミングの台頭やThunderbolt 5の登場など、技術の進歩が私たちの選択肢を広げる一方で、かえって「何を選ぶべきか」を迷わせる側面もあります。皆さんなら、この変化する技術環境の中で、どのような働き方やエンターテインメントスタイルを選択されますか。ぜひSNSでご意見をお聞かせください。