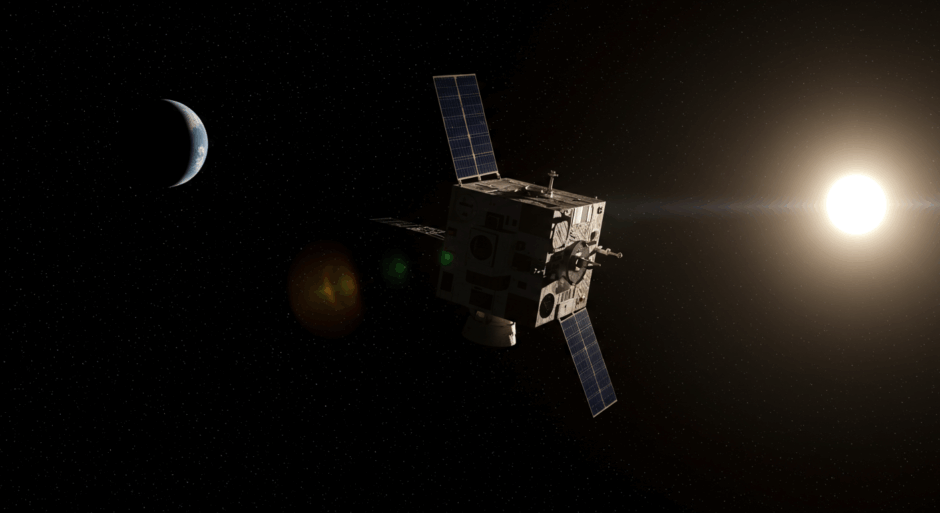NASAのLunar Trailblazer探査機について、同機関は2025年7月末にミッション回復努力の終了を宣言した。
この探査機は2025年2月26日、SpaceX Falcon 9ロケットでIntuitive Machines社の第2回ロボット月着陸機との相乗りで打ち上げられた。打ち上げから約48分後にロケットから正常分離し、通信を確立したが、翌日には接触を失った。太陽電池パネルが太陽に対して適切に向けられておらず、バッテリーが消耗した結果、宇宙船はゆっくりと回転しながら深宇宙に漂流した。
南カリフォルニアのNASAジェット推進研究所のAndrew Kleshプロジェクトシステムエンジニアによれば、月をはるかに超えて漂流する中で太陽電池パネルがより多くの日光を受ける可能性があったが、7月末までに回復の見込みがないことが判明した。仮に無線機を起動する電力があったとしても、信号は地上管制が受信するには弱すぎる状況であった。
この探査機は総額5500万ドル未満というNASAのSIMPLEx(Small Innovative Missions for Planetary Exploration)プログラムの一環として開発された。同プログラムは、月面の水の高解像度マッピングと水の形態、量、時間変化の調査を目的としていた。SIMPLExは低コスト・高リスク戦略を採用し、監視・管理要件を緩和してコスト削減を図るプログラムである。
From:  Lunar Trailblazer trails off as NASA loses probe to the void
Lunar Trailblazer trails off as NASA loses probe to the void
【編集部解説】
宇宙開発において、このLunar Trailblazerの失敗は単なる「宇宙探査の失敗例」以上の意味を持つことをお伝えしたいと思います。
この件は、現在NASAが進める低コスト・高リスク戦略の実態を示すケーススタディとして重要です。SIMPLExプログラムは総額5500万ドル未満という厳格な制約下で科学成果を狙う取り組みですが、コスト削減のため従来の監視体制や管理要件を大幅に緩和しています。今回の失敗は、その「高リスク」部分が現実化した典型例と言えるでしょう。
技術的な観点から見ると、問題は基本的な姿勢制御システムの故障でした。太陽電池パネルが太陽を向かず、バッテリーが消耗して通信が途絶えるという、実は宇宙開発では珍しくない障害です。しかし、低コストミッションでは冗長性の確保が困難で、一つの故障がミッション全体の失敗に直結してしまいます。Intuitive Machines社の第2回月面着陸機「Athena」との相乗りミッションとして実施されたことも、主導権を持てない制約要因の一つだったと考えられます。
月面水資源探査における影響を考えると、この失敗により貴重な科学データの取得機会が失われました。月面の水は将来の有人探査や資源利用にとって極めて重要な要素で、Artemis計画の実現にも直結する情報です。高解像度での水分布マッピングが数年遅れることで、月面基地建設や宇宙資源利用の計画にも影響が生じる可能性があります。
国際的な月面探査競争への示唆も見逃せません。ispaceの「HAKUTO-R」ミッションも、今年6月に月面着陸に再び挑むも失敗しており、民間企業による低コスト宇宙開発の難しさが浮き彫りになっています。一方で、中国はChang’e-6サンプルリターンミッションで月面裏側からの試料回収に成功するなど、技術競争の激化を物語っています。
長期的な視点では、この失敗が宇宙開発戦略の見直しを促す可能性があります。1990年代末のNASA「faster, better, cheaper」戦略と同様の道筋を辿る懸念もありますが、Mars Sojournerローバーのような成功例もあり、完全否定は適切ではありません。重要なのは、民間企業の参入や技術革新により、低コスト宇宙開発の成功確率を向上させることです。
この失敗から得られる教訓を次のミッションに活かすことが何より重要です。NASAは原因調査を継続しており、設計や運用手順の改善につながることが期待されます。宇宙開発において失敗は避けられませんが、それを糧にして技術を向上させる姿勢こそが、人類の宇宙進出を支える原動力となるのです。
【用語解説】
SIMPLEx:
Small Innovative Missions for Planetary Explorationの略。NASAが運営する低コスト・高リスクの惑星探査プログラムで、180kg以下の小型探査機を総額5500万ドル未満で開発し、他のミッションの副次ペイロードとして打ち上げることを特徴とする。
CLPS:
Commercial Lunar Payload Servicesの略。NASAが商業企業に月面輸送サービスを発注する商用月面ペイロード・サービス・プログラム。Intuitive MachinesやFirefly Aerospaceなどが参加している。
faster, better, cheaper:
1990年代にNASAのダニエル・ゴールディン長官が導入した経営方針。開発期間短縮、技術向上、コスト削減を同時に実現することを目的とし、より小型で安価なミッションを頻繁に実施する戦略。Mars Sojournerローバーの成功とMars Polar Landerの失敗を生んだ。
アルテミス計画:
NASAが主導する国際月面探査計画。月面有人着陸と持続的な月面基地建設を目指し、月面の水資源利用が重要な要素となっている。
相乗りミッション:
一つのロケットで複数の探査機や衛星を同時に打ち上げるミッション形態。コスト削減が可能だが、主ペイロードの都合に合わせる必要があり、運用上の制約が生じる。
【参考リンク】
NASA Lunar Trailblazer(外部)
月面水マッピング探査機の公式ミッションページ。科学目標と最新状況を掲載
Intuitive Machines(外部)
テキサス州の宇宙探査企業。第2回月面ミッションでの相乗り打ち上げを実施
Firefly Aerospace(外部)
小型ロケット開発企業。NASAから1億7700万ドルの月面ミッション契約を受注
NASA Mars Pathfinder(外部)
1997年成功のMars Sojournerローバー。低コスト戦略の成功例
【参考記事】
NASA’s Lunar Trailblazer Moon Mission Ends(外部)
NASA公式による正式なミッション終了発表。技術者コメントと今後の教訓
NASA’s Lunar Trailblazer mission ends in disappointment(外部)
Engadgetによる技術的詳細分析。姿勢制御システムの故障メカニズムと低コスト宇宙開発の課題について専門的視点から解説
【編集部後記】
今回のLunar Trailblazerの失敗を見て、皆さんはどのような感想を抱かれたでしょうか?低コスト宇宙開発は果たして「安かろう悪かろう」の典型例なのでしょうか、それとも失敗を糧として技術革新を推進する新しいアプローチなのでしょうか。
日本のispaceも今年「HAKUTO-R」で同様の挫折を経験しましたが、これらの失敗事例から私たちは何を学び取ることができるでしょうか。宇宙開発における「コスト削減」と「ミッション成功」、そして「リスクと挑戦」の適切なバランスについて、ぜひ皆さんの率直なご意見をSNSでお聞かせください。