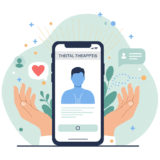ジョージア大学ロースクール受託法講座主任のVictoria Haneman教授は、故人のデジタルデータに対する削除権の必要性を主張している。
生成AIの発達により、Seance AI、StoryFile、Replika、MindBank Ai、HereAfter AIなどの企業が個人のデジタルファイルを学習し、故人の声や容姿を再現するサービスを提供している。Haneman教授は今年初めにボストンカレッジ法学雑誌で「デジタル復活の法律(The Law of Digital Resurrection)」で、この新たな課題に警鐘を鳴らす。
この問題の背景には、米国の約68%もの成人が遺言書なしで亡くなるという現実がある。 改正統一受託者デジタル資産アクセス法(RUFADAA)もデジタル復活への対処は限定的である。パブリシティ権は約25州で死者を保護するが、効果は限定的だ。
ヨーロッパでは人間の尊厳が基本権とされ、フランスやイタリアでは故人のデータ削除権が段階的に導入されている。米国では修正第1条との兼ね合いで同様の権利導入は困難とされる。カリフォルニア州では昨年、生存者向けの削除法が施行された。Haneman教授は12ヶ月の期間限定でのデータ削除権創設を提案している。
From:  The dead need right to delete their data so they can’t be AI-ified, lawyer says
The dead need right to delete their data so they can’t be AI-ified, lawyer says
【編集部解説】
生成AIの驚異的な発展により、私たちは人類史上初めて「デジタルでの死後蘇生」という問題に直面しています。この技術は一見すると感動的な追悼の形に見えるかもしれませんが、その裏側には複雑な法的・倫理的課題が潜んでいることを理解する必要があります。
現在、米国では約60%以上の人々が遺言書なしでこの世を去ります。つまり、故人のデジタル遺品の扱いはテック企業のサービス利用規約(TOSA)に委ねられているのが現状です。Facebookの追悼化機能のように、プラットフォーム側の判断で故人のデジタル痕跡が永続化される仕組みが一般的となっており、遺族の意向とは無関係に処理が進む可能性があります。
改正統一受託者デジタル資産アクセス法(RUFADAA)は、3段階の階層(オンラインツール、遺言書での明示的な許可、裁判所命令)で遺族によるデジタル資産へのアクセスを規定していますが、デジタル復活という新たな脅威に対する保護機能は限定的です。特に電子通信の内容については、より厳格なプライバシー基準が適用されるため、遺族でも簡単にはアクセスできません。
興味深いことに、地域による法的アプローチの違いが顕著に現れています。ヨーロッパでは人間の尊厳を基本権として位置づけ、GDPR第17条の「忘れられる権利」を故人にも適用する動きが見られます。フランスやイタリアでは既に故人のデータ削除権が段階的に導入されており、相続人が故人のデジタルデータにアクセスし、削除を要求できる法的枠組みが整備されています。
一方、米国では修正第1条(言論の自由)との兼ね合いで、同様の権利導入が困難視されています。2024年に施行されたカリフォルニア州の削除法(Delete Act)は、生存者がデータブローカーに対してワンストップで個人データの削除を要求できる画期的な制度ですが、死者への適用拡大については依然として不透明です。
AIによるデジタル復活の技術的特性も重要な考慮点です。従来のデータベースとは異なり、大規模言語モデルは学習データを数十億のパラメータに分散して「記憶」するため、特定の個人データを完全に除去することは技術的に極めて困難です。データが一度AIモデルに組み込まれると、そのモデルをゼロから再訓練することなしに「忘却」させることは実質的に不可能に近いのです。
Haneman教授が提案する12ヶ月という期間限定の削除権は、技術的実現可能性と社会的利益のバランスを考慮した現実的なアプローチと評価できます。人間の遺体に対する法的保護をモデルとしたこの提案は、物理的遺品の処分権と同じ論理をデジタル領域に拡張する試みとして注目されています。
この議論は単なる法的問題を超え、テクノロジーが人間の尊厳と記憶にどう関わるべきかという根本的な問いを投げかけています。innovaTopiaの読者の皆様には、このような先端技術と法制度の交錯点で生まれる新たな課題を理解し、デジタル社会における人権の在り方について考察を深めていただきたいと思います。
【用語解説】
RUFADAA(改正統一受託者デジタル資産アクセス法):
死者や行為能力を失った者のデジタル資産に対して、遺言執行者や受託者などの受託者がアクセスする権限を定めた米国の統一法。3段階の階層(オンラインツール、遺言書での明示的許可、裁判所命令)で遺族によるアクセスを規定するが、電子通信の内容については厳格な制限が存在する。
パブリシティ権:
個人の氏名、画像、肖像の無断商用利用に対する私法上の権利。約25州で故人に対しても適用されるが、収益化には多くの問題が存在する。
修正第1条:
米国憲法に定められた言論の自由を保障する条項。忘れられる権利など、データ削除を求める規制がこの条項に違反する可能性があるとして、米国での導入を困難にしている。
大規模言語モデル:
膨大なテキストデータで訓練されたAIモデル。学習データを数十億のパラメータに分散して記憶するため、特定の個人データを完全に除去することは技術的に極めて困難である。
【参考リンク】
Seance AI(外部)
GPT-4を使用して故人との会話を可能にするAIサービス
StoryFile(外部)
AIを活用した会話型ビデオ技術で個人の物語を保存するサービス
Replika(外部)
3000万人以上のユーザーを抱える生成AIチャットボットアプリ
HereAfter AI(外部)
バーチャルインタビューアーによる音声記録サービス
カリフォルニア州プライバシー保護庁(外部)
削除法(Delete Act)の実施を担当する州政府機関
【参考記事】
The Law of Digital Resurrection – Boston College Law Review(外部)
Victoria Haneman教授によるデジタル復活を規制する法的枠組みの論文
Everything you need to know about the California Delete Act – OptIQ.AI(外部)
2024年1月1日に施行されたカリフォルニア州削除法の詳細解説
Should India Have a Law to Ban Recreating the Dead with AI – NMA Legal(外部)
インドにおけるデジタル復活の法的課題を分析した記事
Digital twin platform MindBank AI lands $1.2M government grant – Refresh Miami(外部)
MindBank AIが米空軍から120万ドルを獲得したニュース
Everything you need to know about the California Delete Act – Didomi(外部)
2023年10月10日に署名された削除法の詳細解説
【編集部後記】
いかがでしょうか。私たちが日々当たり前のように蓄積しているデジタル痕跡が、将来的にAIによって「復活」される可能性があることを、皆さんはどう感じられますか?
今回の記事で特に興味深いのは、技術の進歩と人間の尊厳の間で生まれる新たな課題です。もし皆さんが故人となった時、ご自身のSNS投稿やメッセージ履歴からAIが作られることを望まれるでしょうか?それとも、静かに忘れ去られることを選択されるでしょうか?
現在、この問題に対する明確な法的保護はほとんど存在しません。私たち一人ひとりがデジタル遺品について考え、家族と話し合うことが重要な時代になっているのかもしれません。皆さんのご意見やお考えをお聞かせいただけたら幸いです。