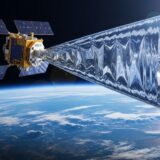オーシャン・アライアンスのクジラ科学者イアン・カーは、クジラの鼻水を採取するために6つのペトリ皿を装着したドローン「スノットボット」を開発した。クジラの鼻水にはDNA、ホルモン、マイクロバイオームなどの情報が含まれている。
2010年のメキシコ湾ディープウォーター・ホライズン石油流出事故の調査中、カーはマッコウクジラの組織サンプル採取に苦労した末にクジラの鼻水を浴びるという経験をした。その際、ドローンを用いて上空から採取するアイデアを得たという。
過去10年から15年でドローン技術は手頃な価格で使いやすくなり、オレゴン州立大学海洋哺乳類研究所の生態学者ジョシュア・スチュワートによれば、科学者は海洋哺乳類研究のほぼすべての側面でドローンの応用を見出している。デューク大学ニコラス環境学部の海洋保全生態学者デビッド・ジョンストンは、ドローンが「まったく新しい視点」を提供すると述べる。
2025年、ワシントン州沖で撮影された9時間のドローン映像から、25頭のシャチが昆布を使って互いにグルーミングする行動が発見された。この研究はワシントン州フライデーハーバーのクジラ研究センターの行動生態学者マイケル・ワイスによって報告された。現在、カーのチームは漁網に絡まったクジラを解放するための3Dプリント製金属切断フックを開発中である。
【編集部解説】
今回のニュースは、海洋生物研究における技術革新の最前線を示しています。ドローン技術が研究手法そのものを根本から変えつつある様子が見えてきます。
従来、クジラの健康状態を調べるには、ボートで接近して組織サンプルを採取する必要がありました。しかしこの方法は動物にストレスを与え、研究者自身も危険に晒されるという問題がありました。ドローンによる非侵襲的なアプローチは、こうした課題を一挙に解決しています。
特に注目すべきは、スノットボットが収集する呼気サンプルの情報量です。DNA配列から妊娠ホルモン、ストレスホルモン、マイクロバイオームまで、これまで入手困難だった生物学的データを網羅的に取得できます。オーシャン・アライアンスはこれまでに5カ国で6種のクジラから355以上のサンプルを収集し、米国各地の研究機関と分析を進めています。
技術的な制約も存在します。小型ドローンのバッテリー持続時間は45分から1時間程度で、多くの国では目視範囲内での飛行が義務づけられています。しかし2025年現在、AI搭載ドローンによるリアルタイム検出・分類技術の開発が進み、人間の専門知識とAIの処理速度を融合した次世代システムが登場しつつあります。
この技術の真価は、科学の民主化にもあります。比較的安価で操作しやすいドローンは、世界中の研究者や学生に海洋生物研究への門戸を開いています。漁網からのクジラ救出といった実用的な応用も視野に入っており、観察から介入へと研究の範囲が広がっています。
【用語解説】
スノットボット(SnotBot)
オーシャン・アライアンスが開発した、クジラの呼気(鼻水)を採取するためのドローンシステム。呼気にはDNA、ホルモン、マイクロバイオームなどの生物学的情報が含まれている。
ディープウォーター・ホライズン石油流出事故
2010年メキシコ湾で発生した、史上最大級の海洋石油流出事故。この事故が契機となり、クジラへの影響調査の新たな研究手法の必要性が認識された。
非侵襲的研究手法
研究対象となる動物に物理的な接触や侵入を伴わない観察・データ収集方法。ドローンによる上空からの観察や呼気採取は、従来のボートでの接近や組織サンプル採取と比較して動物へのストレスを大幅に軽減する。
アロケルピング(Allokelping)
シャチが昆布を使って互いにグルーミングする行動。海洋哺乳類における協力的な道具使用として初めて記録された。
【参考リンク】
Ocean Alliance公式サイト(外部)
世界初の鯨類保護団体の一つ。SnotBot等ドローン研究を推進し、海洋環境保護に注力。
Knowable Magazine(外部)
Annual Reviewsが編集する科学系オンラインメディア。査読情報を一般向けに発信。
Center for Whale Research(外部)
ワシントン州拠点。シャチを中心に個体群モニタリングや行動研究を長年継続。
NOAA Fisheries(外部)
米国の海洋生物保全・調査を担当する政府機関。近年はドローン技術活用に注力。
Duke University Nicholas School of the Environment(外部)
地球科学・環境政策・海洋保全を担う米国大学院部門。ドローン研究も推進。
【参考動画】
【参考記事】
Killer whales groom each other—with pieces of kelp | Science | AAAS(外部)
ワシントン州で30回観察されたシャチの昆布グルーミング行動の研究とドローンによる新発見について詳細解説。
Drones for Whale Research: SnotBot | UN SDGs(外部)
5カ国6種のクジラから355以上のサンプルを収集したスノットボット関連SDGsパートナー事例と成果。
Using Drones and Tags to Study Rice’s Whales | NOAA Fisheries(外部)
ライスクジラへのドローンを使ったタグ装着の成功事例。調査効率・正確性向上の過程を紹介。
【編集部後記】
クジラの呼気を収集するドローン技術は、単なる研究手法の革新にとどまりません。動物にストレスを与えず、人間も危険を冒さずに済むこのアプローチは、私たちが自然とどう向き合うべきかを問いかけているように感じます。みなさんは、こうした非侵襲的な観察技術が、他にどんな分野で活かされると思いますか?野生動物の保護から都市部の生態系モニタリングまで、可能性は広がっています。