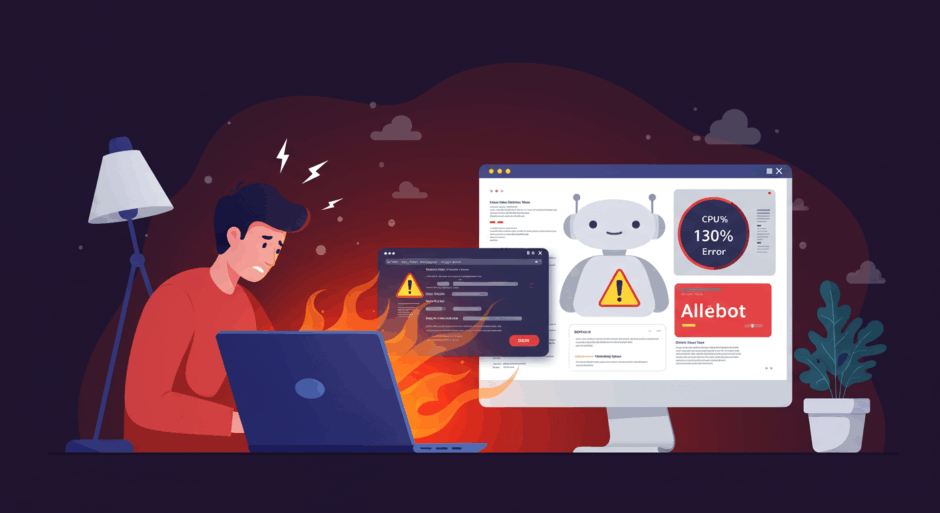2025年8月13日、The Registerが報じたところによると、一部のFirefoxユーザーがCPUパワーと電力の大量消費を報告している。原因は最近のFirefoxバージョンに組み込まれた「推論エンジン」とみられる。MozillaはFirefoxにLLMボットを埋め込み、タブグループの名前付け機能を提供している。ユーザーは「Inference」と呼ばれるバックグラウンドプロセスによるCPUと電力使用量のスパイクを報告している。
Firefox 138でタブグループ機能が導入され、Firefox 141では「AI強化タブグループ」機能が追加された。この機能は開いているタブのタイトルと説明を読み取り、タブとグループ名を提案する。処理はすべてデバイス上で行われる。
Bugzillaではバグ #1982278でこの問題が追跡されている。Mozilla広報担当者は段階的ロールアウト中に意図せずパフォーマンスバグを出荷したことを認め、ロールアウトを取り消したと発表した。ユーザーは「about:config」で「browser.ml.enable」設定を切り替えることで、すべてのローカル推論機能を無効にできる。
From: Some users report their Firefox browser is scoffing CPU power
Some users report their Firefox browser is scoffing CPU power
【編集部解説】
今回のFirefoxのAI機能によるパフォーマンス問題は、Webブラウザが本来の役割を超えて「何でもできる」プラットフォーム化していく現在の技術潮流を象徴する事例と言えます。
実は、Mozillaが2025年7月22日にリリースしたFirefox 141に実装した「Inference」と呼ばれる推論プロセスは、単なるタブグループ機能だけでなく、より大きなAIランタイム基盤の一部なのです。Mozilla公式ドキュメントによると、このシステムはTransformers.jsとONNXランタイムエンジンに基づく実験的な機械学習推論システムで、ウェブページの翻訳機能など、複数の用途で使用されています。
今回の問題で注目すべきは、ユーザーから報告されたCPU使用率の具体的な数値です。複数のソースによると、Inferenceプロセスは通常時の0.05%から最大130%まで大幅に変動しており、これは明らかに異常な動作パターンを示しています。なお、CPU使用率が100%を超える数値は、マルチコア環境において複数のコアを同時使用していることを表しています。
Mozilla側の対応を見ると、同社は段階的ロールアウト中に「意図しないパフォーマンスバグ」を出荷したことを認めています。興味深いのは、このバグがテスト段階では発見されなかったという点で、実際のユーザー環境の多様性と複雑さを浮き彫りにしています。
技術的観点から見ると、MozillaはMicrosoftのOpen Neural Network Exchange(ONNX)フォーマットを採用していますが、複数の技術メディアでは他のより効率的なフォーマットと比較して最適化が不十分だったのではないかという指摘もあります。ローカル推論は確かにプライバシーの観点では優れていますが、計算リソースとのトレードオフが課題となっています。
また、Mozilla広報担当者はInferenceプロセスについて「言語翻訳などのプライベートなオンデバイスAI推論を担当する分離されたプロセス」と説明しており、この機能がタブグループ機能以外にも使用されていることが明確になりました。
このような問題は、AI機能の統合において「何のために」という根本的な問いを投げかけています。タブグループの名前付けという比較的単純なタスクに対して、高度なAI推論を使用する必要性について、多くのユーザーが疑問視しているのも当然でしょう。
長期的な視点では、この事例はブラウザベンダー各社がAI統合を進める際の重要な教訓となりそうです。機能の価値とリソース消費のバランス、そしてユーザーの選択権の尊重が、今後のAI統合において鍵となる要素だと言えるでしょう。
Mozillaは既にロールアウトを取り消し、修正に取り組んでいると発表していますが、この問題は単なるバグ修正を超えて、AI機能の実装アプローチそのものを見直すきっかけになるかもしれません。innovaTopiaの読者の皆さんにとっては、プライバシーを重視するFirefoxがどのような方向性でAI統合を進めていくのか、注意深く観察していく価値がある展開と言えるでしょう。
【用語解説】
Inference(推論)
機械学習において、訓練済みモデルを使って新しいデータに対して予測や判断を行うプロセスである。Firefox内では、AIモデルがタブの内容を分析してグループ名を提案する際に使用されている。
LLM(Large Language Model)
大規模言語モデルの略で、膨大なテキストデータで訓練された深層学習モデルである。Firefoxでは、タブグループの命名機能などに組み込まれている。
段階的ロールアウト(Phased Rollout)
新機能をすべてのユーザーに同時に展開するのではなく、段階的に対象を拡大していく配信手法である。Mozillaはこの方式でAI強化タブグループ機能を展開している。
about:processes
Firefoxの内部状態を確認するための診断ページで、ブラウザが実行中のプロセスとそのCPU使用率を表示する。アドレスバーに「about:processes」と入力することでアクセスできる。
about:config
Firefoxの高度な設定を変更するための管理画面である。通常のユーザーインターフェースでは設定できない詳細な項目を調整できる。
Transformers.js
JavaScriptで実装されたTransformerモデルのライブラリで、ブラウザ上でAI推論を実行するために使用される。
Douglas Adams
『銀河ヒッチハイク・ガイド』シリーズで知られるイギリスのSF作家である。記事中では、彼とJohn Lloydが著した『The Meaning of Liff』から「Ely」という用語が引用されている。
【参考リンク】
Mozilla Firefox公式サイト(外部)
非営利組織Mozillaが開発する無料のウェブブラウザ。プライバシー重視とカスタマイズ性の高さで知られる
Mozilla公式サイト(外部)
Firefoxブラウザの開発元である非営利組織の公式サイト。人々のためのインターネットを理念に掲げる
ONNX Runtime公式サイト(外部)
Microsoftが開発するクロスプラットフォーム機械学習モデルアクセラレータ。FirefoxのAI推論エンジンの基盤技術
Mozilla Support日本語版(外部)
Firefox日本語版の公式サポートサイト。ブラウザの設定方法、トラブルシューティングなど詳細な解説を提供
【参考記事】
Firefox’s New AI Feature Is Causing Major CPU Spikes and Draining Batteries(外部)
Firefox v141.0のAIタブグループ機能がCPU使用率0.05%から130%まで変動する問題を詳細に報告
New local AI integration into Firefox spurs complaints of ‘CPU going nuts’(外部)
Tom’s Hardwareによる技術的分析記事。2025年7月22日リリースのFirefox 141の問題経緯を時系列で整理
【編集部後記】
今回のFirefoxの問題を通じて、私たちが普段何気なく使っているブラウザにも、知らないうちにAI機能が搭載されていることがわかりました。皆さんは、便利さとプライバシー、そしてデバイスのパフォーマンスのバランスをどう考えられますか?
もしかすると、お使いのブラウザでも同様の現象が起きているかもしれません。
一度【about:processes】で確認してみてはいかがでしょうか。
また、AI機能を無効にするか残すか、その判断基準について、ぜひSNSで教えてください。
技術の進歩と日常の使いやすさ、どちらを優先すべきか、一緒に考えていけたら嬉しいです。