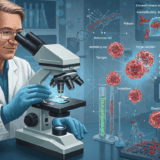現代の交通インフラにおいて、信号機はあまりにも当たり前の存在となっています。私たちは毎日、赤・黄・青の光によって示される指示に従い、安全に道路を行き交っています。しかし、この「当たり前」が確立されるまでには、長い技術発展の歴史がありました。8月20日は「交通信号設置記念日」です。この記念日を機に、人類の移動を支えるテクノロジーの進化を振り返り、未来への展望を探ってみたいと思います。
「交通信号設置記念日」の概要
8月20日は「交通信号設置記念日」として制定されています。この記念日の由来は、1931年(昭和6年)8月20日に、東京・銀座の尾張町交差点(現在の銀座4丁目交差点)や京橋交差点など34ヶ所に、日本初の3色灯の自動信号機が設置されたことに遡ります。
この日の設置は、単なる交通整理の手段の導入にとどまらず、日本の交通安全文化が大きく前進した歴史的瞬間でした。当時は電車以外の通行者は色灯による交通信号を理解できず従わなかったそうです。それもそのはず、大正半ばから昭和初期にかけては、警察官の「挙手の合図」や「信号標板」によって交通整理が行われていたので、色灯の信号機は見たことがなかったのです。
実は日本初の自動交通信号機は、1930年(昭和5年)3月23日に東京の日比谷交差点に設置された米国製のもので、灯器を交差点の中央に設置する中央柱式でした。この信号機には「ススメ」「チウイ」「トマレ」と文字が書かれており、3色灯の意味を知らせる工夫がされていました。しかし、1931年8月20日に設置されたものが「3色灯の自動信号機」として、より実用的な形での本格運用の始まりを象徴する日となっています。
信号機の歴史:技術発展の側面から
世界初の信号機:ガス式から電気式へ
交通信号の歴史は、産業革命とともに急速に発展した都市交通の課題解決から始まりました。灯火方式による世界初の信号機は、1868年、ロンドン市内のウエストミンスターに設置された信号機です。これは光源にガスを使い、緑色と赤色を手動で表示するものでした。この信号は馬車の交通整理のために置かれましたが、起動から3週間後に爆発事故を起こし、撤去されています。
この初期の試みは失敗に終わりましたが、交通制御の必要性は変わりませんでした。19世紀のロンドンでは馬車による交通事故が多発しており、1866年には1000人以上が死亡し、1300人を超える市民が負傷していたという深刻な状況が、技術革新への動機となっていました。
電気式信号機の時代は20世紀に入って本格化します。1914年8月8日、オハイオ州クリーブランドに世界初の電気式信号機が設置されました。そして1918年、アメリカのニューヨーク5番街に、現在につながる赤・黄・緑の3色灯式信号機が初めて設置されました。この時点で、既に現在と同じ3色システムの基礎が確立されていました。
日本における信号機の発達
日本の信号機発展は、海外技術の導入から始まり、独自の改良を重ねる過程でした。日本の交通信号機は、大正8年(1919年)、東京・上野に「信号標板」が試験設置されたことが始まりです。これは「進メ」と「止レ」の標板を付けた手動式の標識で、大正11年(1921年)から実用を開始しました。
技術的な進歩は着実に続きました。1934年(昭和9年)7月には「押しボタン式信号機」が登場しました。東京市蒲田区の国道1号(現在の東京都大田区の国道15号)の梅屋敷前と六郷郵便局前に設置され、横断する人が少ない交差点では車を優先させるために、道路を渡る人がボタンを押して信号を切り替えるシステムが導入されました。
1955年(昭和30年)9月には「音響信号機」が登場しました。東京都杉並区の東田町交差点にベルの鳴動による音響式信号機が設置され、目の不自由な人も横断歩道を安心して渡ることができるように、青信号では音が鳴るシステムが実装されました。
さらに、1963年(昭和38年)3月には、信号待ちの車を自動的に感知する「感応式信号機」が東京と横浜で設置されました。いかにもクルマ社会の日本ならではのアイデアでした。
LED革命:21世紀の技術革新
信号機技術における最大の革新の一つが、LED(発光ダイオード)の導入です。1993年に青色LEDが発明され、そこから発展して屋外での使用にも耐えうる青色LEDが開発されました。1994年7月、愛知県名古屋市の市役所交差点に、世界初のLED式青色矢印信号機が設置されたのを皮切りに、信号機にもLEDの使用が開始されました。
LED化のメリットは多岐にわたります。信号機のLED化によって、消費電力がこれまでの60 Wの白熱電球のものと比べて3分の1から10分の1程度にまで抑制できるようになりました。またLEDは電球と比べ長寿命であり、電球と比べると頻繁にメンテナンスをする必要がなく、そのためメンテナンス費用の削減にも繋がりました。
技術的な改良も継続的に行われています。2017年(平成29年)度には、警察庁が車両用信号機の表示面の直径の標準を300mmから250mmに変更しました。これにより、信号機の横幅が200mm縮まり、ひさしも省略されています。その結果、製造コストが約17%削減されたほか、約6割の軽量化でコンパクトとなりました。
日本独自の技術的工夫
日本の信号機は、単なる海外技術の模倣にとどまらず、独自の工夫を重ねてきました。
横型信号機の採用
信号機の形を横型にしたのも日本独自のアイデアです。最初に米国から持ち込まれた信号機は縦型でしたが、やがて京都市の交差点に横型の信号機が設置されました。全国有数の観光地である京都は、道路標識、看板、そして街路樹も多かったため、縦型の場合、一番上の赤信号が見づらかったのです。そのために3色を横並びにしたという実用的な理由がありました。
色覚障害への配慮
技術的進歩は、社会のバリアフリー化とも歩調を合わせています。LED信号機では色覚障害に配慮して黄色は青色・赤色と比べ明るく点灯します。また、信号機の表示を分かりやすくするために赤表示の部分に「×」印を付けた信号機が考案され、2012年(平成24年)に福岡市で試験設置されました。この「×」印は色覚障害者にのみ見えるものです。
積雪地域への対応
日本の多様な気候条件に対応するため、地域特有の課題も技術で解決しています。LED化により発熱量が小さくなったため、雪が解けずに付着し見づらい・見えないという問題が発生するようになりました。信号機に雪が付着しないようにお椀型の透明な着雪防止フードを灯器に取り付けて視認性を確保する場所や、約6 cmの薄い板状にした「フラット型信号灯器」を斜め下に向けて設置して対策を行う場所が見られます。
未来の信号機:AI・IoT時代への展望
AI搭載による自律的制御
現在開発が進められている次世代信号機の核心は、AI(人工知能)による自律制御です。NEDOと(一社)UTMS協会は「人工知能技術適用によるスマート社会の実現」事業において、電波レーダーやプローブ情報(位置情報)から取得した交通情報などを活用する人工知能(AI)を組み込んだ適応型の自律・分散交通信号機による交通管制方式の確立に取り組んでいます。
この技術により、従来の課題が解決される可能性があります。現在の信号機は、曜日や時間帯によって周期が変わる「プログラム多段制御」や交通管制センターに集まった情報をコンピューターが分析し、各信号機に指示を出す「集中信号機制御システム」などにより渋滞解消を図っています。しかし、これらの交通システムでは突発的な混雑には対処できず、渋滞が生じてしまうことが往々にしてあります。
5G・IoT技術との融合
未来の信号機は、5G通信やIoT技術と密接に連携することで、より高度な交通制御を実現します。IoT技術や無線通信技術の向上により、例えば、この自律分散型信号機制御の場合、信号機にAIや道路状況を把握するためのセンサーを組み込むため、デバイスは小型化・省電力化されるべきです。これはまさにIoT技術です。また離れた機器同士を連携させるには、電波を飛ばさなければならず、しかも大量のデータを素早く飛ばす必要があります。これまでの100倍の速さで情報交換が行え、同時に多くのものと接続できる次世代通信規格5Gの活用も期待されています。
自動運転社会への対応
未来の信号機は、自動運転車との協調を前提として設計されます。現在、クルマの自動運転時代を見据え、クルマと信号機とが相互に情報をやり取りし、円滑な交通を目指す研究が進められています。この技術により、車両は信号の切り替えタイミングを事前に把握し、最適な速度で走行することが可能になります。
環境負荷削減への貢献
スマート信号機は、交通流の最適化を通じて環境負荷削減にも貢献します。渋滞は交通状況を混乱させるだけでなく、渋滞が原因による経済損失、アイドリング時に排出される二酸化炭素による環境汚染など、時間・経済・資源の多方面において様々な悪影響を及ぼします。AI制御により、これらの問題の大幅な軽減が期待されています。
歴史的意義と未来への示唆
テクノロジーの民主化
信号機の歴史は、高度な技術の民主化過程でもあります。最初はガス灯という贅沢品から始まり、電気、そしてLEDへと発展する過程で、より安価で効率的、かつ誰もが利用できる公共インフラとなりました。AI信号機も同様の道筋をたどり、最終的には世界中の都市で標準的な技術となる可能性が高いと考えられます。
Society 5.0への架け橋
内閣府が実施しNEDOが管理法人を務めるSIP第2期「自動運転(システムとサービスの拡張)」や、PRISM「交通信号機を活用した5Gネットワークの構築」とも連動して、自動運転や高速大容量通信の実現をはじめとするSociety 5.0時代に求められる交通管制システムを確立し、既存システムからの進化を目指しています。信号機は単なる交通制御装置から、デジタル社会の基盤インフラへと進化しつつあります。
人間中心設計の重要性
技術の進歩とともに重要になるのが、人間中心設計の視点です。システムが進歩したとしても、利用するのはあくまでも人間です。人が制御しているのか、AIが制御しているのかは見た目では分からないでしょうが、急にシステムが切り替われば混乱をきたすことは想像に難くありません。未来の信号機設計においても、この観点は極めて重要です。
まとめ
この進化は、人類の移動と社会活動を支える基盤技術の発展史そのものでもあります。ガス式信号機の爆発事故から学んだ安全性の重要性、LED化による省エネルギー技術、そして現在開発が進むAI制御システムまで、すべてが「人間の安全で効率的な移動」という一貫した目標に向かっています。
未来の信号機は、私たちが想像する以上に高度で複雑なシステムになるでしょう。しかし、その根底にあるのは、1868年のロンドンで初めて設置されたガス式信号機と同じ「交通の安全と円滑化」という願いです。テクノロジーは進歩しますが、人間を中心とした設計思想は変わりません。これこそが、技術進歩の真の価値なのかもしれません。
交通信号設置記念日に際し、私たちは改めて「当たり前」に感謝し、その背後にある技術革新の歴史と未来への展望に想いを馳せたいと思います。そして、人類の進化を促進するテクノロジーとして、信号機が果たしてきた、そしてこれから果たすであろう役割を再認識すべきです。