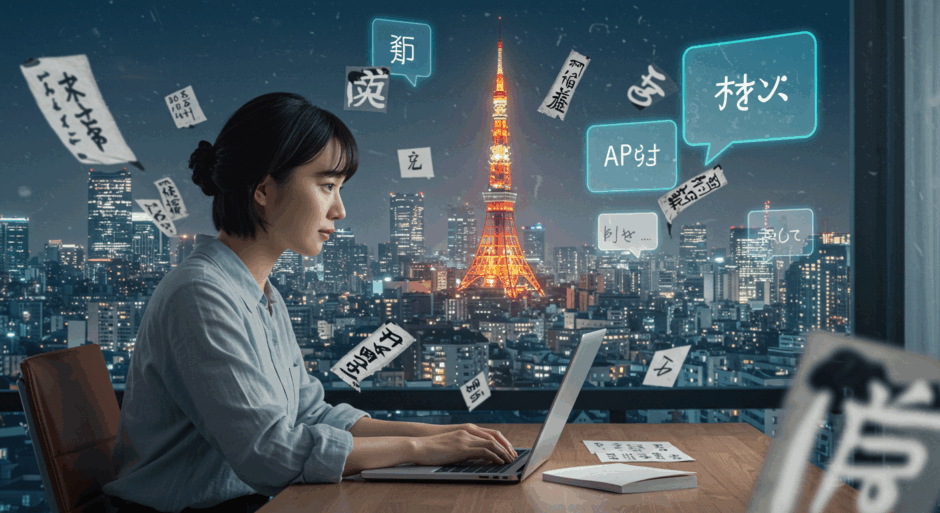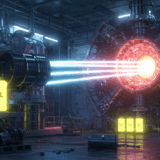日本の小説家九段理江(34歳)が『東京都同情塔』の英訳出版を前に、ChatGPTを使った小説執筆について語った。同作品は2024年に芥川賞を受賞した九段の4作目の小説である。作品の約5%がChatGPTで執筆されており、登場人物とChatGPTのやりとりとして提示された部分で構成される。小説は日本人建築家サラ・マキナが有罪判決を受けた犯罪者を収容する塔の建設を委託される内容である。九段は2022年に『スクールガール』で芥川賞候補になったが受賞しなかった。執筆のきっかけの一つは2022年7月の安倍晋三元首相暗殺事件である。作品では犯罪者への同情とカタカナ表記の増加が主要テーマとなる。九段は1990年生まれで、現在AIが人間の作家より優れた小説を書くことは不可能だと述べている。先月の日本の選挙で極右政党参政党が参議院で1議席から14議席に議席を伸ばした。『東京都同情塔』は8月21日にペンギン・ブックスから£10.99で発売される。
From: Author Rie Qudan: Why I used ChatGPT to write my prize-winning novel
Author Rie Qudan: Why I used ChatGPT to write my prize-winning novel
【編集部解説】
innovaTopiaPの読者の皆さんもよくご存知のように、AIと文学の交差点は近年最もホットな議論の一つですが、九段理江さんの事例は単なる技術活用を超えた深い社会的意味を持っています。
この記事で最も注目すべきなのは、九段さんが「AIに代替される恐れ」ではなく「AIを通じて何を伝えるか」という創作者としての明確な意図を持っていることです。彼女の場合、ChatGPTの使用は隠蔽工作ではなく、むしろ現代社会における言語の変化とその政治的影響を読者に示す手法として機能しています。
興味深いのは、この論争が技術的な問題から社会言語学的な議論に発展していることです。記事で言及されている「参政党」の躍進は実際に2025年7月の参院選で確認されており、同党が1議席から14議席へと大幅に議席を伸ばしました。九段さんが指摘するカタカナ表記の政治的利用は、まさに現在進行中の現象なのです。
文学界における反応も二分されています。一部からは「盗作」との批判があった一方で、ChatGPTが賞金を分け合うべきだというユーモラスな意見まで出ています。しかし重要なのは、九段さんがその後95%をAIで執筆する実験作品「影の雨」を発表するなど、境界を押し広げ続けていることです。
この事例が示すポジティブな側面として、AIは作家の創作プロセスを効率化し、新たな表現領域を開拓する可能性があります。特に多様な背景を持つ作家たちにとって、AIツールは創作への参入障壁を下げる効果も期待されています。
一方で潜在的なリスクも見逃せません。著作権の帰属、創作の真正性、そして人間の創造性の定義そのものが問われています。特に文学賞の審査基準や、出版業界の価値判断にも長期的な影響を与える可能性があります。
規制面では、現在のところ明確な法的枠組みは存在せず、各文学賞の運営委員会や出版社が個別に対応している状況です。しかし今後、AI使用の明示義務化や、AIと人間の協働作品に対する新たなカテゴリー設定なども議論される可能性が高いでしょう。
九段さんの挑戦は、文学というアナログな芸術領域において「テクノロジーとの共存」という現代的課題を先駆的に提示しており、まさに「Tech for Human Evolution」を体現する事例といえるのではないでしょうか。
【用語解説】
芥川賞
日本の純文学を対象とした最も権威のある文学賞の一つ。正式名称は「芥川龍之介賞」で、新人・新進作家を対象とする。半年に一度選考が行われ、受賞者は文壇での地位が確立される。
ChatGPT
OpenAIが開発した対話型人工知能システム。大規模言語モデル(LLM)を基盤とし、自然な対話や文章生成が可能。2022年11月の公開以降、世界中で生成AIブームを牽引している。
参政党
2020年に設立された日本の政党。「日本人ファースト」をスローガンに掲げ、2025年の参議院選挙で1議席から14議席へと大幅に議席を拡大した。
カタカナ
日本語の表音文字の一つで、主に外来語や外国語の音写に使用される。ひらがなや漢字と比べ、より中性的で婉曲的な印象を与えるとされる。
同情塔
小説『東京都同情塔』に登場する架空の施設。犯罪者を人道的に収容する目的で建設される塔で、現代社会の犯罪者への同情や処罰のあり方を象徴的に描いた舞台設定である。
【参考リンク】
OpenAI(外部)
ChatGPTを開発したアメリカのAI企業。GPTファミリーやDALL-Eなどの生成AIモデルを提供し、2022年のChatGPT公開で生成AIブームを牽引した。
Penguin Books UK(外部)
1935年創立の英国の出版社。『東京都同情塔』英語版の出版社で、ペンギンクラシックスシリーズをはじめ世界中で親しまれる書籍を出版している。
The Guardian(外部)
1821年創刊の英国の日刊紙。リベラルな論調で知られ、文学・文化分野の報道にも定評がある。デジタル版は世界中で読まれている。
【参考記事】
AI fiction is already here. Are humans ready?(外部)
九段理江のAI使用について詳細に報道。2024年1月の芥川賞受賞時の記者会見での告白や、小説の約5%がChatGPTで執筆されたことを確認している。
Far-right ‘Japanese First’ party Sanseito emerges as fourth-largest opposition force in parliament(外部)
2025年7月の日本参議院選挙で参政党が1議席から14議席に躍進した詳細を報告。「日本人ファースト」スローガンの政治的影響について分析している。
Rie Qudan, AI, and the Future of Human Authorship in Literature(外部)
九段理江のAI使用が文学界に与えた影響を分析。受賞後の論争や、その後の実験的作品「影の雨」(95%をAIで執筆)についても言及している。
Exploring the Impact of AI on Fiction Writing(外部)
AI技術が創作活動に与えるポジティブな影響とリスクを包括的に分析。作家の創作プロセス効率化と著作権問題の両面を検討している。
【編集部後記】
この記事を読んで、皆さんはどう感じられたでしょうか。九段理江さんの挑戦は、私たちが普段何気なく使っている言語や、創作活動そのものの定義を揺さぶる出来事だと思います。
特に印象的だったのは、AIを隠すのではなく、むしろそれを通じて現代社会の問題を浮き彫りにしようとする姿勢です。皆さんは日常でカタカナ表記を見かけた時、そこに込められた意図について考えたことはありますか?
また、もし皆さんが創作者だとしたら、AIをどのように活用したいと思われますか?
それとも、完全に人間だけの創作にこだわりたいでしょうか?
ぜひSNSで、皆さんの率直なご意見をお聞かせください。一緒に「創作とテクノロジーの未来」について考えていけたら嬉しいです。