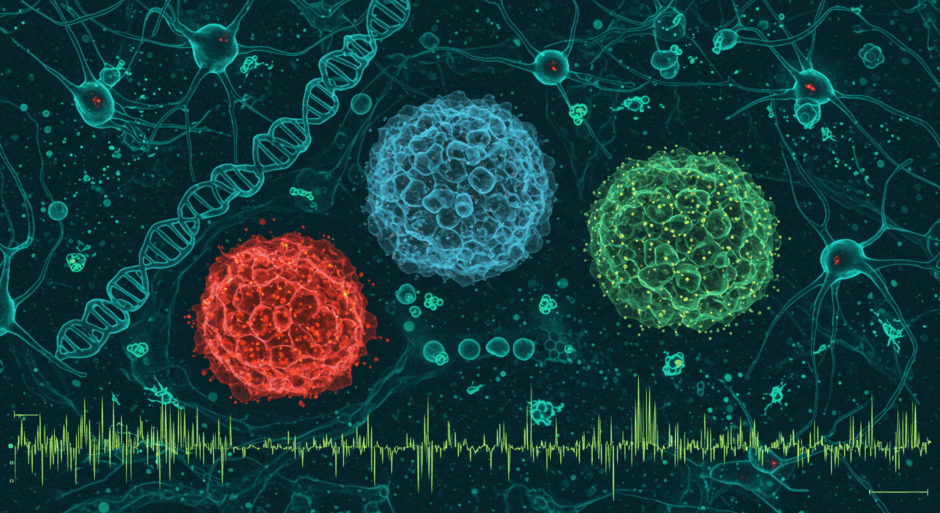ワシントン大学の神経科学者Katherine Prater氏とKeビン Green氏らの研究チームが、アルツハイマー病患者12名と健康な対照群10名の脳解剖検査サンプルを用いてミクログリアの遺伝子活動を分析した結果を発表した。単核RNA配列解析を強化する新手法により、脳組織内の10の異なるミクログリアクラスターを特定した。このうち3つのクラスターは未発見のもので、1つがアルツハイマー病患者により多く見られた。アルツハイマー病患者の脳では、ミクログリアが炎症前状態にある頻度が高く、炎症と細胞死に関与する遺伝子がオンになっていることが判明した。これらのミクログリアは保護機能が低下しており、死んだ細胞や老廃物の除去能力が損なわれている。研究結果は2023年に発表され、Nature Aging誌に掲載された。Prater氏は特定のミクログリアクラスターが新たな治療標的になる可能性があると述べている。
From:  Brain Autopsies Revealed a Potential Culprit Behind Alzheimer’s
Brain Autopsies Revealed a Potential Culprit Behind Alzheimer’s
【編集部解説】
今回発表された研究は、アルツハイマー病の病理メカニズムにおいて、これまで見落とされていたミクログリアの多様性に光を当てた画期的な発見です。従来のアルツハイマー病研究では、ミクログリアの役割は「保護的」か「炎症性」かという二元論で捉えられることが多かったのですが、この研究は遺伝子発現レベルでの詳細な分析により、その認識を大きく変える可能性があります。
最も注目すべき点は、単核RNA配列解析という先端技術を駆使して、これまで発見されていなかった3つの新しいミクログリアクラスターを特定したことです。特に、アルツハイマー病患者により多く見られるクラスターでは、炎症と細胞死に関与する遺伝子群が活性化されていることが明らかになりました。これは、従来の抗炎症薬がアルツハイマー病治療で期待されたほどの効果を示さなかった理由の一端を説明する可能性があります。
この発見が持つ技術的意義は極めて大きく、個別化医療への道筋を示しています。患者ごとのミクログリアの遺伝的プロファイルを解析することで、より精密な治療戦略の立案が可能になるでしょう。
一方で、「ミクログリアが病理を引き起こしているのか、病理がミクログリアを変化させているのか」という根本的な因果関係については、まだ明確な答えは得られていません。この疑問は、治療戦略の選択において重要な意味を持ちます。
今後期待される展開としては、特定のミクログリアクラスターを標的とした新しい治療法の開発があります。特に、CRISPR技術を用いてミクログリアを改変し、病的な環境でのみ治療効果を発揮させるアプローチが注目されています。このような技術革新により、副作用を最小限に抑えながら効果的な治療が実現する可能性が高まっています。
【用語解説】
ミクログリア
脳に存在する免疫細胞で、老廃物の除去と正常な脳機能の維持に関与する。感染や死細胞の除去に反応して形状を変化させ、侵入者や老廃物を貪食する能力を持つ。
単核RNA配列解析
個々の細胞の遺伝子発現を詳細に解析する先端技術。従来の手法では見分けることができなかった細胞の微細な違いを特定できる。
炎症前状態
完全な炎症反応を起こす前の準備段階にある細胞状態。この状態の細胞は炎症分子を産生しやすく、組織損傷を引き起こす可能性が高い。
Nature Aging
加齢研究分野の権威ある国際学術誌。老化メカニズムや年齢関連疾患に関する最新研究成果を掲載している。
TREM2
ミクログリア表面に発現する受容体で、アルツハイマー病のリスク遺伝子として知られる。正常に機能するとアミロイドβの除去を促進するが、機能不全になると病理が進行する。
【参考リンク】
ワシントン大学(外部)
1861年設立の米国西海岸最古の公立大学の一つ。医学、工学、科学研究で世界的に知られる
Nature Aging(外部)
世界的権威を持つNature出版グループの加齢研究専門誌
【参考記事】
The dual role of microglia in Alzheimer’s disease(外部)
アルツハイマー病におけるミクログリアの二面性について包括的にレビューした2025年の論文
Unraveling the complex role of microglia in Alzheimer’s disease(外部)
アルツハイマー病におけるミクログリアのアミロイドβ代謝の複雑な役割を統合的に解析
Transcriptional and epigenetic decoding of the microglial aging process(外部)
3~24ヶ月齢のマウスを用いてミクログリアの老化過程を転写・エピジェネティックレベルで解析
The VCAM1–ApoE pathway directs microglial chemotaxis(外部)
IL-33がミクログリアのVCAM1を誘導し、アミロイドβプラーク関連ApoEへの化学走性を促進
【編集部後記】
今回のミクログリア研究の発見は、私たちの脳の中で起きている複雑な現象の一端を明らかにしました。単核RNA配列解析という技術によって、これまで見えなかった細胞の多様性が浮き彫りになったのです。
この研究成果が将来的にどのような治療法につながるのか、また私たち一人ひとりの脳の健康にどのような意味を持つのか、皆さんはどう考えられますか?
アルツハイマー病の予防や治療における技術革新の可能性について、ぜひご一緒に考えてみませんか。