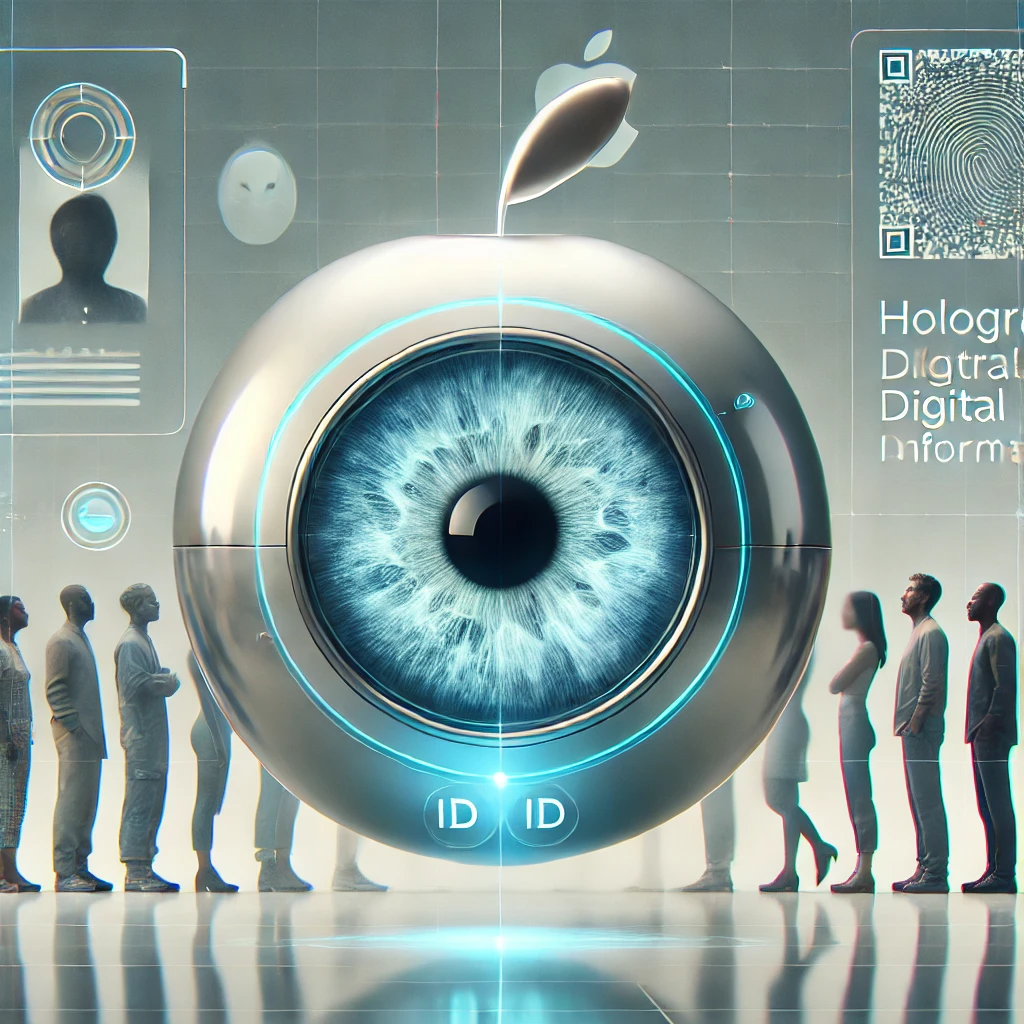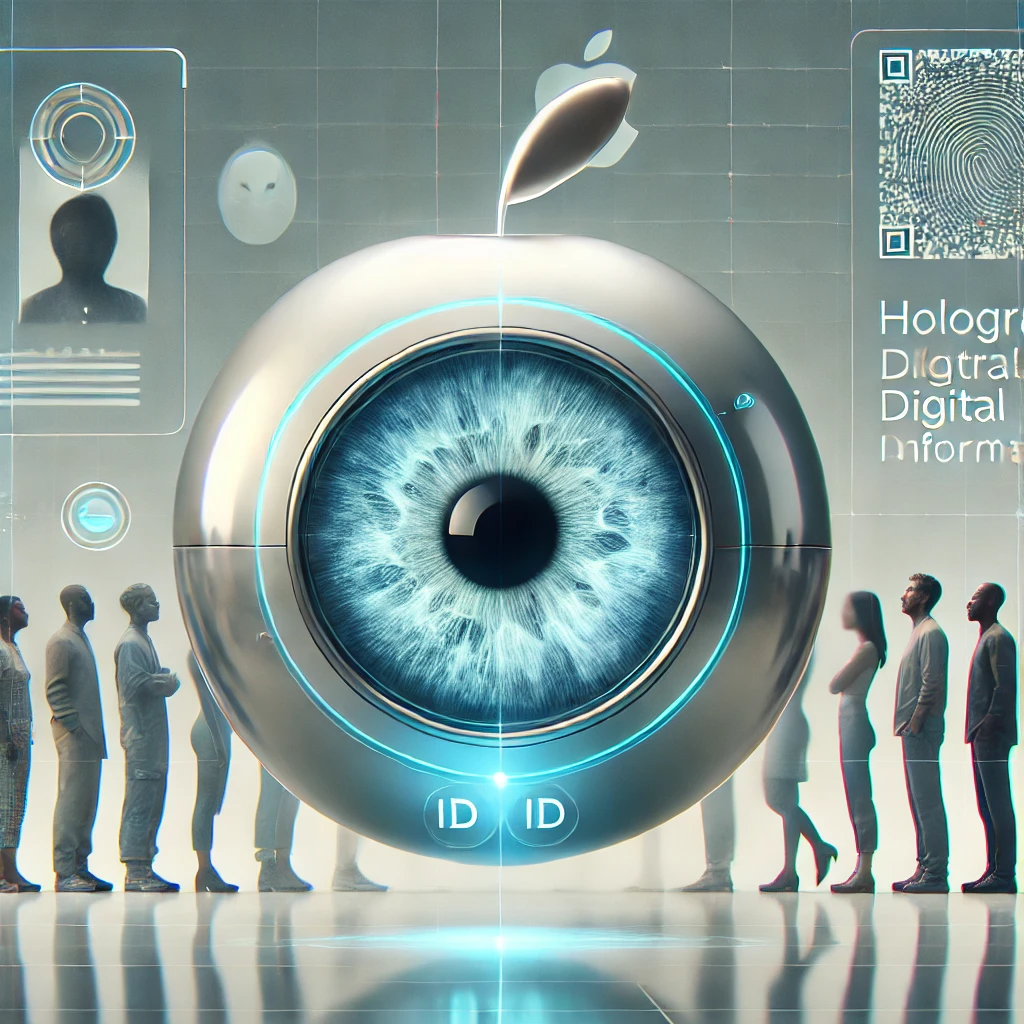2021年に導入されたIEEE 2089-2021は、5Rights原則に基づく年齢適切デジタルサービスフレームワーク標準で、国連児童の権利に関する条約に基づき子供向けオンライン製品・サービスの適格化手順を提供する
これらの動きを受け、各国で法制化が進んでいる。インドネシアは2025年3月、IEEE標準化協会との協力のもと
欧州でも規制強化の動きが加速している。ギリシャは未成年者をオンラインの危険から保護するための国家戦略を開始し、フランスやスペインと共にEUレベルでの包括的な年齢認証システムの導入を強く推進している
From: IEEE Makes Strides to Improve Online Safety for Kids It offers age-verification standards and a certification program
【編集部解説】
今回のIEEEによる子供向けオンライン安全標準の取り組みは、単なる技術標準の策定を超えて、デジタル社会における「子供の権利」という概念を実装可能な形で定義した画期的な動きです。
この標準化の背景には、従来の「保護者任せ」のアプローチでは限界があるという現実があります。UNICEFの統計によると世界のインターネットユーザーの3人に1人が18歳未満である現在、プラットフォーム側の設計思想そのものを変革する必要性が高まっていました。
技術標準が実現する具体的な保護機能
IEEE 2089.1-2024が定義する6つの評価指標は、年齢認証技術の精度向上を目指すものです。特に注目すべきは「頻度」という概念を導入している点で、一度の認証で永続的にアクセスを許可するのではなく、定期的な再認証を求める仕組みを標準化しています。
これにより、例えば兄弟間でのデバイス共有や、成長に伴う年齢区分の変更にも柔軟に対応できるようになります。従来のクッキーベースの年齢確認では不可能だった、動的な年齢認証システムの構築が可能になったのです。
アジア初の法制化が示すグローバルトレンド
インドネシアが2025年5月に法制化した児童保護規制は、IEEE標準を直接的に法律に反映した世界初の事例として重要な意味を持ちます。この規制では、オンラインサービスプロバイダーがプラットフォームの設計と実践において子供の最善の利益を優先することを義務付けています。
5Rights Foundationによると、これはアジア初の年齢適切設計規制であり、各国の文化的コンテキストに応じた標準の適用が可能であることを証明しています。IEEE事務局長のSophia Muirheadは、この協働を「IEEEがその使命を実践的な方法で実行し、社会と子供のニーズを支援する例」と評価しています。
ギリシャの取り組みが示す政府主導アプローチ
ギリシャが最近開始した未成年者オンライン保護戦略は、民間企業に依存しない政府主導のアプローチとして注目されます。IEEE標準と専門知識を活用したこの戦略には、年齢認証とコンテンツフィルタリングのシステムを含む包括的な規制フレームワークが含まれています。
ギリシャ首相のKyriakos Mitsotakisは、現在のオンライン環境を「私たちの子供と十代の若者のメンタルヘルスに対する前例のない世界的実験」と表現し、システムのアルゴリズムが中毒を促進するように設計されていることを問題視しています。
認証プログラムがもたらす業界変化
IEEE SAが英国のAge Check Certification Schemeと提携して開始した認証プログラムは、年齢認証技術の品質保証メカニズムを市場に導入しました。これまで各社が独自に実装していた年齢認証システムに、統一された評価基準と第三者認証という概念を持ち込んだ意義は大きいものです。
この認証制度により、企業は年齢認証システムの導入において「IEEE準拠」という明確な指標を得られるようになり、規制当局や保護者に対する説明責任を果たしやすくなります。同時に、認証を受けたシステム間での相互運用性向上も期待されます。
長期的視点での課題とリスク
しかし、この技術標準化には潜在的なリスクも存在します。最も重要なのは、厳格な年齢認証がデジタルデバイドを拡大する可能性です。公的身分証明書へのアクセスが限られた地域や家庭の子供たちが、デジタルサービスから排除される懸念があります。
また、政府主導の年齢認証システムは、国家による若者のオンライン活動監視の手段として悪用される可能性も指摘されています。特に権威主義的な政権下では、年齢認証の名目で表現の自由や情報アクセス権が制限される危険性があります。
未来のデジタル社会設計への影響
この動きは単なる子供保護策を超えて、デジタルサービス設計の根本的な変革を促しています。5Rights FoundationのBeeban Kidron議員が指摘するように、「100%設計された世界」であるデジタル空間を、意図的に子供に適したものとして再設計する取り組みが始まっています。
彼女は、規制が反応的なツールや保護者制御に依存するのではなく、効果的なデフォルト設定を通じてシステムの設計・開発そのものに焦点を当てるべきだと主張しています。これは将来的に、年齢に応じて動的に変化するユーザーインターフェースや、成長段階に合わせた段階的な機能開放といった、より洗練された年齢適応型デジタルサービスの実現につながる可能性があります。
技術標準の国際的な普及により、グローバルなデジタルプラットフォームも統一された子供保護機能の実装を求められることになり、結果として世界中の子供たちがより安全なデジタル環境を享受できる基盤が整いつつあります。
【用語解説】
5Rights
年齢保証(Age Assurance)
デフォルト設定
児童性的虐待コンテンツ(CSAM)
国連児童の権利に関する条約
【参考リンク】
IEEE Standards Association
5Rights Foundation
Age Check Certification Scheme
IEEE Online Age Verification Certification Program
UNICEF – Children’s Rights Convention
【参考動画】
VIDEO
Age Check Certification Scheme公式チャンネルによるIEEE 2089.1オンライン年齢認証標準について、標準の概要と実装指針を専門家が解説している公式プレゼンテーション動画。
【参考記事】
Indonesia joins global effort to protect children from unregulated technology
Greek Prime Minister urges EU regulatory action against algorithmic exploitation of children
【編集部後記】
みなさんはお子さんのデジタル機器利用について、どのようなルールを設けていらっしゃいますか?今回のIEEE標準化の動きを見ていて、技術による保護と家庭でのルール設定のバランスについて考えさせられました。
特に気になるのは、政府主導の年齢認証システムが普及した場合、私たち保護者の役割がどう変化するのかという点です。技術に頼り切ってしまうリスクもある一方で、適切に活用すれば子育ての強い味方になる可能性も感じています。
みなさんのご家庭では、お子さんのオンライン体験をどのように見守っていますか?
デジタルアイデンティティニュースをinnovaTopiaでもっと読む サイバーセキュリティニュースをinnovaTopiaでもっと読む