メタバース技術の最大の課題はスケーラビリティだった。RobloxやMeta Horizon Worldsは1サーバーあたり40ユーザーという制限に縛られ、この技術的制約がメタバースの真の可能性を阻害してきた。
RP1が発表したメタバースブラウザは、この根本的な問題への解答だ。独自のStatabase技術により単一環境で10万ユーザーの同時接続を実現し、従来のシャード分割アーキテクチャの限界を突破している。
メタバース領域では、これまでプラットフォーム依存型のクローズドエコシステムが主流だった。しかしRP1は、WebXR技術を基盤とした分散型ホスティングモデルにより、真にオープンな空間インターネットの構築を目指している。
この技術革新により、メタバース体験はアプリダウンロード不要でウェブブラウザから直接アクセス可能になる。地球全体の1:1スケールデジタルツインと完全な6DOF空間オーディオを統合したこのプラットフォームは、メタバース技術の次世代標準となる可能性を秘めている。
空間コンピューティング企業のRP1が6月9日(現地時間、日本時間6月10日)に世界初のメタバースブラウザを発表した。
カリフォルニア州ロングビーチに拠点を置くRP1は、空間インターネット向けの革新的なブラウザ技術を公開した。同社の共同創業者兼CEOのショーン・マンによると、このブラウザは従来の平面的なウェブサイト閲覧から、AR・VRデバイスを通じた3D空間コンテンツ閲覧への転換を可能にする。
RP1のメタバースブラウザは、現在のRobloxやMeta Horizon Worldsなどの3Dプラットフォームが1インスタンス・サーバーあたり40ユーザーに制限されているのに対し、世界中の全人口を単一のシャード分割されていないアーキテクチャで接続可能な前例のないスケーラビリティを実現しようとしている。同社は過去に4000ユーザーの同時接続デモを実施し、現在は10万ユーザーの同時接続が可能だと主張している。
技術的特徴として、地球の1対1スケールのデジタルツインから太陽系全体、宇宙の果てまでを含む無限のマップ機能、AI・決済・ゲーム・ビジネスサービスなどのサードパーティサービスと連携するリアルタイムAPI、企業が自社サーバー上で独自のワールドやサービスを運営できる分散型ホスティング機能を備えている。
同社は独自のリアルタイムネットワーキングとStatabase技術により、ユーザーがあらゆるデバイスで即座にストリーミングされる没入型3D環境を体験できるとしている。WebXR技術を採用することで、アプリケーションのダウンロードやインストールを必要とせず、ウェブブラウザから直接3D空間にアクセス可能になる。
RP1は2023年のWebXRアワードで「イノベーション・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、2024年のVRアワードでも複数の賞にノミネートされた実績を持つ。同社はAWE USA 2025でブース528においてデモを展示している。
Sawhorseの共同創業者兼最高イノベーション責任者のニック・ヒルは、このソリューションがXRやUGCゲーム分野で活動するスタジオ、ブランド、エージェンシーの障壁や制限を取り除く可能性があると評価している。Virtual World Society理事のリンダ・リッチも過去に同社の技術について高い評価を示している。
from:
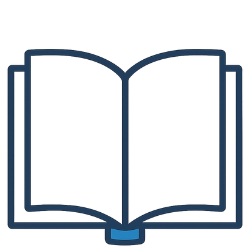 RP1 Launches the World’s First Metaverse Browser | Business Wire
RP1 Launches the World’s First Metaverse Browser | Business Wire
【編集部解説】
RP1は2020年頃から空間コンピューティング分野で活動しており、2022年には4000ユーザー同時接続のデモを成功させ、現在は10万ユーザーの同時接続を実現していると報告されています。
最も革新的な点は、従来のメタバースプラットフォームが抱える根本的なスケーラビリティ制約を解決していることです。現在のRobloxやMeta Horizon Worldsといった主要プラットフォームでは、1つのサーバーインスタンスあたり40名程度のユーザーしか同時接続できません。これに対してRP1は、独自のStatabase技術により単一のシャード環境で10万人以上のユーザーを同時接続可能だと実証しています。
技術的な革新性の核心は、WebXRベースのアーキテクチャと独自のネットワーキング技術にあります。ユーザーはアプリケーションをダウンロードすることなく、ウェブブラウザから直接3D空間にアクセスできます。これは現在のウェブサイト閲覧と同様の手軽さで、没入型の3D体験を提供することを意味し、従来のアプリストア依存モデルからの大きな転換点となります。
RP1の創業チームは、オンラインポーカーゲームの大規模ネットワーキング技術を10年以上開発してきた経験を持ちます。この背景が、従来の1000倍のハードウェア効率で大規模同時接続を実現する技術基盤となっています。実際のデモでは、仮想空間から現実世界のデバイス(照明など)を制御する機能も確認されており、IoT統合による産業応用の可能性を示しています。
しかし、WebXRベースのメタバースプラットフォームには重要なセキュリティ課題も存在します。日本のスマートフォンセキュリティフォーラムの研究によると、メタバース環境では従来のウェブセキュリティに加えて、アバターのなりすまし、空間内での盗聴・盗撮、仮想オブジェクトの不正取得といった新たな脅威が確認されています。特にWebXR技術では、ブラウザのメモリから機密情報が抽出される可能性があり、適切なセキュリティ対策の実装が不可欠です。
RP1のアプローチで特に注目すべきは、分散型ホスティングの概念です。企業が自社のサーバーインフラ上で独自の3D空間を運営できるため、データの所有権と管理権を完全に保持できます。これは現在の閉鎖的なプラットフォームモデルとは対照的で、ウェブの分散型構造に近い形態を実現しています。
地球全体の1対1スケールデジタルツインという機能は、デジタルツイン市場の発展に大きな影響を与える可能性があります。デジタルツイン技術は現実世界の物体やシステムをデジタル空間で正確に再現し、リアルタイムでデータを同期する技術で、製造業、都市計画、医療分野での活用が期待されています。RP1のプラットフォームでは、これらの産業用途とメタバース体験を統合することが可能になります。
長期的な視点では、RP1のような技術が成熟すれば、現在のウェブブラウジングが3D空間ブラウジングに置き換わる可能性があります。メタバース市場は2030年に約1兆ドル規模に達すると予測されており、教育、医療、製造業、エンターテインメントなど、あらゆる分野でのデジタル体験が根本的に変化することになるでしょう。
【用語解説】
メタバースブラウザ:
従来の2Dウェブサイトではなく、3D空間コンテンツを閲覧・操作するためのソフトウェア。AR・VRデバイスやデスクトップから仮想空間にアクセスし、リアルタイムで他のユーザーと交流できる。RP1は世界初の本格的なメタバースブラウザを開発したと主張している。
空間コンピューティング:
物理的な3D空間とデジタル情報を融合させる技術分野。ユーザーの位置や動作を認識し、現実世界に仮想オブジェクトを配置したり、仮想空間内で自然な操作を可能にする。Apple Vision ProやMeta Questなどのデバイスで実現される。
WebXR:
ウェブブラウザ上でVR・AR体験を提供するためのWeb標準技術。専用アプリをダウンロードすることなく、ブラウザから直接没入型体験にアクセスできる。W3Cによって標準化が進められている。
6DOF(6自由度):
3次元空間における物体の動きを表す概念で、前後・左右・上下の移動と、ピッチ・ヨー・ロールの回転を含む6つの自由度を指す。VR・ARにおいて自然な動作追跡に必要な技術要素。
シャード分割:
大規模なオンラインサービスにおいて、サーバーの負荷を分散するためにユーザーを複数のサーバーインスタンスに分割する手法。従来のメタバースプラットフォームで採用されているが、RP1は単一シャード環境を実現している。
Statabase技術:
RP1が開発した独自のリアルタイムネットワーキング技術。従来の1000倍のハードウェア効率で大規模な同時接続を実現し、完全な空間オーディオと6DOFを提供する。
分散型ホスティング:
中央集権的なプラットフォームに依存せず、各企業や個人が独自のサーバーでサービスを運営する方式。データの所有権と管理権を完全に保持できるため、ウェブの分散型構造に近い。
【参考リンク】
RP1公式サイト(外部)空間コンピューティング企業RP1の公式サイト。メタバースブラウザの技術詳細やライブデモ体験が可能。同社の革新的な3Dブラウザ技術について詳しく解説している。
Metaverse Standards Forum(外部)メタバース技術の標準化を推進する業界団体。RP1も参加しており、2025年5月7日に同社の3Dブラウザのデモを実施した。メタバース技術の標準化動向を知ることができる。
AWE(Augmented World Expo)(外部)世界最大級のAR・VR業界カンファレンス。RP1が2025年にメタバースブラウザのデモを展示したイベント。XR業界の最新動向と技術展示を確認できる。
Auganix(外部)XR(拡張現実・仮想現実)業界の最新ニュースと分析を提供する専門メディア。RP1のメタバースブラウザ発表についても詳細な分析記事を掲載している。
【参考記事】
RP1 Launches Metaverse Browser for the Spatial Internet | Auganix
XR業界専門メディアによるRP1のメタバースブラウザ発表に関する詳細分析。技術的特徴や業界への影響について専門的な視点から解説している。
RP1 shows the ability to cover billions of yuan Universe platform | XRCTO
RP1の過去の技術デモンストレーションに関する記事。同社の大規模スケーラビリティ技術の背景と発展経緯について詳しく説明している。
RP1 Shatters Metaverse Limits: Showcases Technology Platform | Business Wire
2023年のRP1による技術プラットフォーム発表に関するプレスリリース。現在のメタバースブラウザ発表に至る技術的基盤について説明している。
【編集部後記】
ウェブブラウザが登場してから30年余り、私たちは平面的な画面の中でデジタル世界を探索してきました。しかし今、その根本的なパラダイムが変わろうとしています。
RP1のメタバースブラウザは、単なる技術的進歩を超えた意味を持っています。これまでメタバースと呼ばれてきた空間の多くは、実際には「島」のような閉鎖的な環境でした。しかしRP1が提示するビジョンは、ウェブのようにオープンで相互接続された空間インターネットです。
特に興味深いのは、同社が「所有権」という概念を重視していることです。現在のプラットフォーム経済では、私たちのデータや創作物は巨大テック企業のサーバーに蓄積され、その企業の判断一つで消失するリスクを抱えています。RP1の分散型アプローチは、クリエイターや企業が真の意味でデジタル資産を所有できる未来を示唆しています。
もちろん、技術的な課題も残されています。10万人同時接続という数字は確かに印象的ですが、実際の商用環境でどこまで安定性を保てるかは未知数です。また、WebXRのセキュリティ課題や、大規模な3D空間におけるプライバシー保護など、解決すべき問題は山積しています。
それでも、RP1の取り組みは明らかに正しい方向を向いています。私たちが次の10年で体験するデジタル世界は、今日のそれとは根本的に異なるものになるでしょう。そしてその変化の最前線で、日本の読者の皆さんにも新たなチャンスが生まれているのです。
メタバースニュースをinnovaTopiaでもっと読む