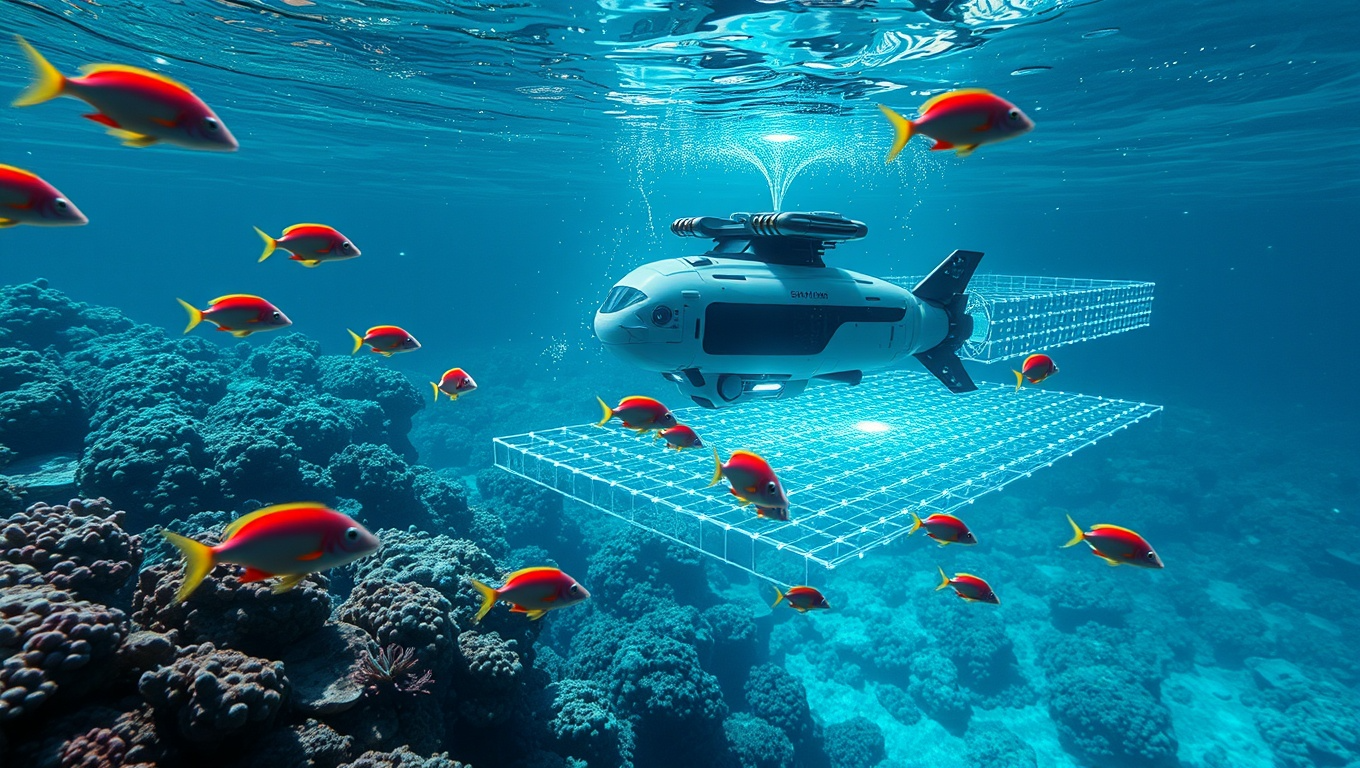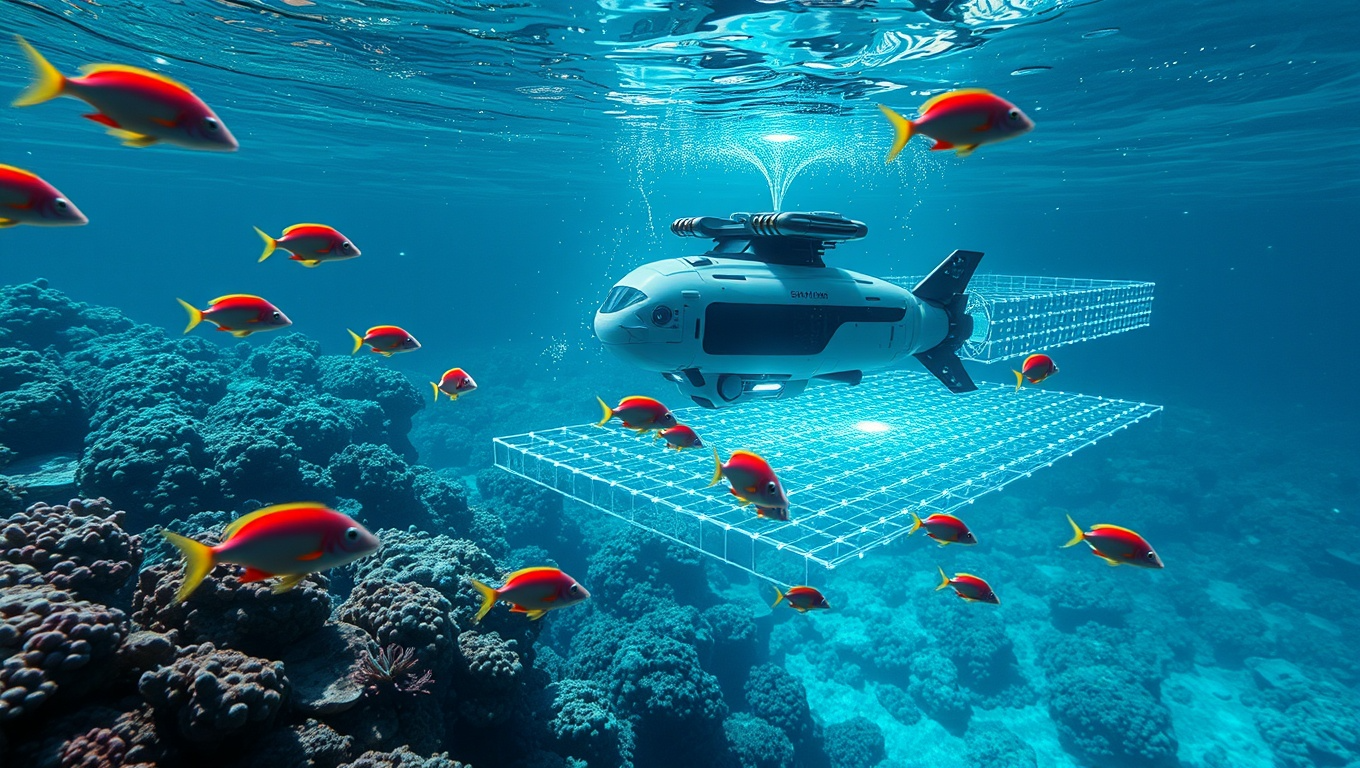プリンストン大学発のAIチップスタートアップEnCharge AIが2025年5月29日、アナログインメモリコンピューティング技術を採用したAIアクセラレータ「EN100」を発表した。
同社はこれまでに1億4400万ドルを調達し、2022年に設立された。EN100はラップトップ、ワークステーション、エッジデバイス向けに設計され、200TOPS以上の計算性能を提供する。
製品はM.2(ラップトップ用)とPCIe(ワークステーション用)の2つの形態で展開される。M.2版は8.25Wの電力制約内で200TOPS以上を実現し、PCIe版は4つのNPUを搭載して約1ペタOPSに達する。
同社CEOのNaveen Verma氏は、従来のデジタルソリューションと比較して約20倍のエネルギー効率を実現すると述べた。
EN100はM.2版が最大32GBのLPDDRメモリと68GB/sの帯域幅、PCIe版が最大128GBのLPDDRメモリと272GB/sの帯域幅を備え、30TOPS/mm²の計算密度を持つ。投資家にはTiger Global、Samsung Ventures、RTX Venturesなどが含まれ、同社の従業員数は60人である。
From: Encharge AI unveils EN100 AI accelerator chip with analog memory
【編集部解説】
アナログインメモリコンピューティングの技術的革新性
EnCharge AIが採用するアナログインメモリコンピューティングは、従来のデジタルチップとは根本的に異なるアプローチを取っています。通常のAIチップでは、メモリから処理ユニットへのデータ転送が大きなボトルネックとなり、これが消費電力増大の主因でした。
同社の技術は、メモリ内で直接計算を実行することでこの問題を解決しています。具体的には、電荷ベースのメモリ読み取り方式を採用し、個別のビットセルではなく電流の合計から計算結果を得る手法により、従来比20倍のエネルギー効率を実現しているのです。
エッジAI市場への戦略的インパクト
この技術革新が最も大きな影響を与えるのは、エッジAI市場における力学の変化でしょう。現在、高度なAI処理の多くはクラウドデータセンターに依存していますが、EN100の登場により、ラップトップやワークステーションレベルでも本格的なAI推論が可能になります。
特に注目すべきは、M.2フォームファクターで200+ TOPSを8.25W以内で実現している点です。これは従来のモバイルGPUでは不可能だった性能密度であり、バッテリー駆動デバイスでの本格的なAI活用に道を開くものです。
産業界への波及効果と新たな可能性
この技術により、これまでクラウド依存だったAIアプリケーションの多くがローカル実行可能になります。リアルタイム画像認識、音声処理、自然言語処理などが、レイテンシやプライバシーの制約なしに実行できるようになるでしょう。
特に自動車産業、産業用ロボティクス、スマートリテールなどの分野では、リアルタイム性が重要な用途において大きな変革をもたらす可能性があります。また、医療機器や防衛システムなど、データの外部送信が困難な分野でも新たな応用が期待されます。
潜在的なリスクと課題
一方で、アナログコンピューティング技術には固有の課題も存在します。デジタル技術と比較して、温度変化や製造ばらつきに対する感度が高く、長期的な信頼性の確保が重要な課題となります。
また、既存のソフトウェアエコシステムとの互換性確保も重要です。同社はPyTorchやTensorFlowサポートを謳っていますが、開発者コミュニティでの採用が進むかどうかが成功の鍵を握るでしょう。
競合環境と市場ポジショニング
興味深いのは、EnCharge AIがNVIDIAやAMDとの直接競合を避け、エッジAI市場に特化している点です。これは賢明な戦略と言えるでしょう。データセンター市場は既存プレイヤーの支配が強固ですが、エッジAI市場はまだ成長途上であり、エネルギー効率という明確な差別化要因を持つ同社にとって有利な戦場となります。
長期的な業界への影響
この技術が広く普及すれば、AI処理の分散化が加速し、クラウドインフラへの依存度が大幅に低下する可能性があります。これは、データプライバシー、エネルギー消費、地政学的リスクなど、現在のAI業界が抱える多くの課題の解決策となり得るのです。
また、計算密度30TOPS/mm²という数値は、将来的にスマートフォンやIoTデバイスへの展開も視野に入れており、AIの民主化という観点からも注目に値する技術革新と言えるでしょう。
【用語解説】
TOPS(Tera Operations Per Second)
アナログインメモリコンピューティング
M.2フォームファクター
PCIeカード
NPU(Neural Processing Unit)
電荷ベースメモリ
【参考リンク】
EnCharge AI公式サイト
プリンストン大学
Tiger Global Management
Samsung Ventures
【参考動画】
VIDEO
【編集部後記】
AIチップの進化は私たちの日常をどう変えていくのでしょうか。EnCharge AIのEN100が示すアナログインメモリコンピューティングは、これまでクラウドに依存していたAI処理をラップトップレベルで実現する可能性を秘めています。皆さんが普段使っているデバイスで、どのようなAI体験を求めていますか?プライバシーを重視したローカルAI処理と、クラウドの利便性、どちらを優先したいと考えますか?この技術革新が実用化された時、最初に試してみたいアプリケーションは何でしょうか?
【参考記事】
SiliconANGLE – EnCharge’s EN100 accelerator chip sets the stage for more powerful on-device AI inference
Business Wire – EnCharge AI Announces EN100, First-of-its-Kind AI Accelerator
AIM Research – EnCharge AI Raises $100 Million To Challenge The AI Chip Status Quo
【関連記事】
半導体ニュースをinnovaTopiaでもっと読む